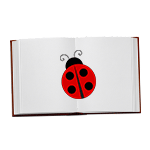あなたは子どもの頃、夏休みや冬休みの宿題を早く終わらせるタイプ😀でしたか?
それとも最終日になってから焦って終わらせるタイプ😅でしたか?
やるべきことをやるべき時にやれば、仕事は円滑に進む

仕事が早い人、遅い人。お客さんからのクレームが多い人、少ない人を観察していて思うことは、両者の違いは、やるべきことをやるべきタイミングでやっているかどうかの違いなのではないか、という結論に落ち着きました。
たとえば、メールの返事を一本返すのでも、すぐに返事ができるような内容であれば、その場で返してしまったほうが楽ですし、メールを送った相手にしても、すぐに返事が来たら有難いです。
ですが、仕事が遅い人というのは、メールを送った相手や、後回しにすると忘れるかもということを考えずに、「今はめんどくさいからいいや」というような理由で、仕事を後回しにします。
その結果どうなるかというと、返答待ちの相手の仕事が進まなくなったり、メールを送ること自体を忘れたりします。
これはメールだけに限らず、
あらゆる仕事において言えます。
顧客の対応が遅れクレームになったりします。
プロジェクトが中々進まない時も、よくよく見てみると、こういう仕事の遅いタイプの人のせいで、動きが止まっている場合があったりします。
感情に任せて仕事をすると、仕事が遅くなる

ではなぜ仕事が遅い人が、やるべきことをやるべきタイミングでできないかというと、彼らのようなタイプは、感情に任せて仕事をしているからです。
「今はめんどくさいから後でやろう」とか、「この人は気難しいから電話したくない」とか。
感情に任せてタスクの優先順位を決めていくと、基本的には重いものばかりがタスクとして山積みされていきます。
さらに、仕事は、一度ドサッと入ってきてそれで終わりではなく、毎日毎日増えていきます。
なので、山積みになったタスクを差し置いて、新たに増えた仕事に手を出してしまうと、いつまでたっても、山積みにされた重いタスクに手を付けられません。
夏休みの宿題を最終日にやる。大人になっても変わらない人たちはクレームの嵐
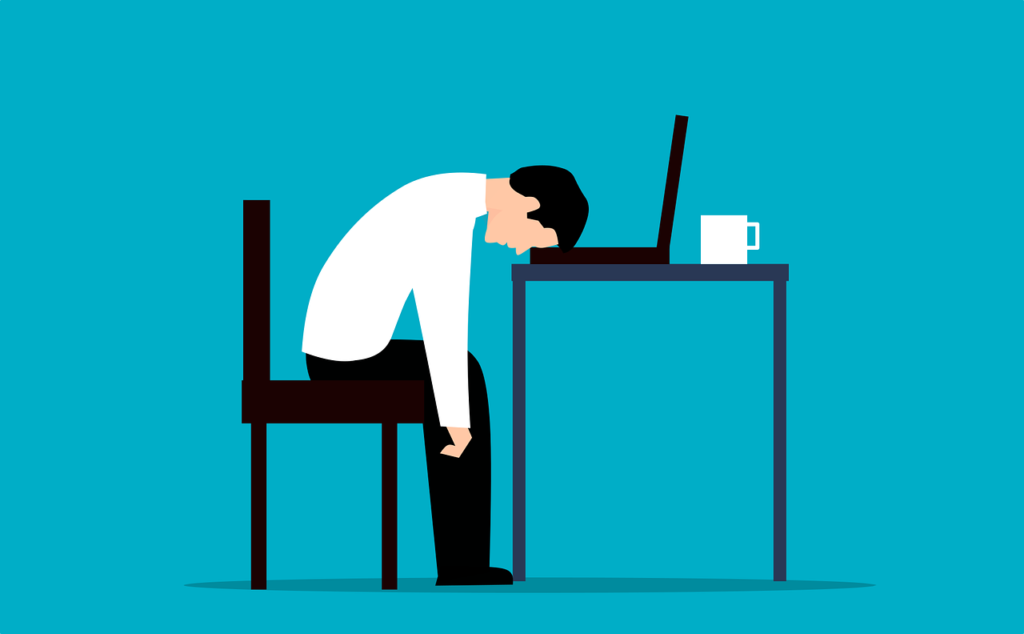
これは皆が皆そうかの確証は取っていませんが、大人になって仕事が遅い人というのは、子どもの頃からタスクの処理が遅かったのではないかと考えられます。
たとえば長期休暇の宿題です。
夏休みや冬休みの宿題。
あなたは子どもの頃、長期休暇の宿題をどのタイミングで終わらせていましたか?
あなたのまわりに、いつも宿題を終わらせるのが遅い人はいませんでしたか?
もしいたとしたら、その人たちは大人になってからどんなビジネスマンになりましたか?
人は変わることができるので、子どもの頃にタスクの処理が遅くても、大人になって速くなることは多々あります。
それに、やるべきことをやるべきタイミングでやるというのは、物理的な速さの問題というよりかは、「やろう!」と思えるかどうか、つまり精神面の問題です。
なのでふつうは、本人の意識さえ変われば見違えるように変わります。
ですから必ずしも、子ども頃と大人になってからが同じまま、ということにはなりませんが、何も変わらずに、自分を変えずに生きてきた人たちは、大人になって、仕事ができないビジネスマンになっているはずです。
年末が忙しいという理由がよくわからない

子どもの頃の私は、夏休みや冬休みの宿題を休みに入る前に8割くらい終了させていました。
なぜなら、何かをやらないといけないという意識が頭の中にあると、楽しく笑えない性格の子どもだったからです。「だった」というか今でもそうです。
自分のこの性格に疲れると感じたこともありますが、今では「こんな自分でよかった」と思えています。
たとえば私は、「年末は忙しい」という世間の常套句の意味がわかりません。
世間の人たちは、大掃除や年賀状、やり残したタスクの処理、来年に向けた準備などがあるため、忙しいと言っているのだと思います。
ただ、私が思うに、そういったことを年末になってやっている時点でアウトです。
そんなものはギリギリになってやるものではなく、事前に終わらせておくものです。
たとえば大掃除。
日々掃除をしていたり、不必要な物を溜め込まないようにしておけば、大掃除なんて必要ないと思いませんか?
私は家で年末の大掃除をしません。
なぜなら日々掃除をしているため、特別年末に掃除する場所がないからです。
たとえば年賀状。
量が多くて大変そうなら、少し前からコツコツとやっておくべきだと思いませんか?
年間休日0の芸能人ならまだわからなくもないですが、ちゃんと週休2日ある人たちの中で「忙しい」と言っている人たちは、日々のタスクが多すぎて忙しいのではありません。
ただ、溜め込み過ぎたタスクをやらざるを得ない状況になって、「忙しい」と言っているだけです。
気持ちとかどうでもいいから、問題に飛び込むこと

仕事が早くなる方法、タスク処理を円滑に進める方法は、感情を捨てることです。
自分の感情でタスクの優先度を決めるのをやめることです。
あとは未来志向を持つことです。
これは投資などにも通ずる考え方ですが、「今、楽するべきか」「後で楽するべきか」を考えるということです。
この2つの選択肢を考えた時に、「後で楽をする」を選べる人は、未来志向を持っていると言えます。
一見すると、時系列をズラしただけで、同じことのように思えますが、全然違います。
「やるべきことをやっていない」と思いつつ遊ぶのと、「やるべきことが終わっている」と安心したうえで遊ぶのとは全然違います。
それに、物事にはトラブルが付き物なので、多少リソースに余裕をみて物事に取り掛からないと、ギリギリになってから手遅れということになりかねません。
たとえば、夏休みの宿題で植物を育てるという課題だったり、星の研究などの課題があったとします。
こういった課題にギリギリで取り掛かった場合、植物の成長が間に合わないとか、3日間連続の雨で全く星が見えないというトラブルに見舞われてゲームオーバーする可能性が考えられます。
それに対して、できるだけ早くタスクに取り掛かることができれば、余裕を持って植物を育てることができますし、晴天の夜を選んで星の観察ができます。
タスクに早く取り掛かるということには、「予期せぬ事態を想定せよ」という意味もあるのです。
まとめ
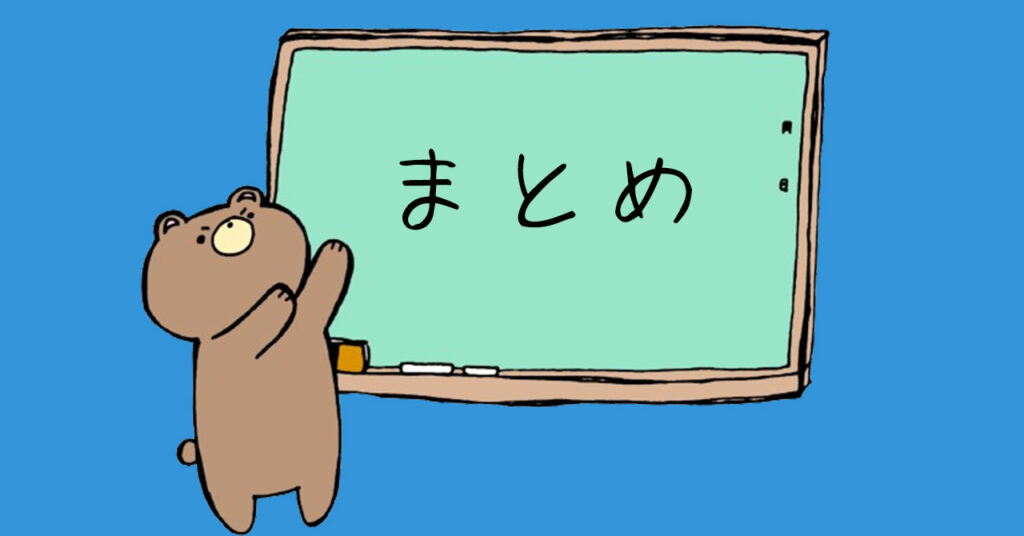
- やるべきことを、やらざるを得なくなってからやるのではなく、やるべき時にやること
- タスクの優先度は感情的に決めてはいけない
- 予期せぬ事態を想定したうえで、できるだけ早くタスクに取り掛かること