 新人Web担当
新人Web担当Web担当を任されました。ホームページで集客するためにはSEO対策が必要と聞いたのですが、SEO対策って何ですか?
 青山
青山SEOマーケターの私にお任せください。基本から応用まで丁寧にご説明します。
この記事では、新人Web担当者を相手に、SEO対策の基本から応用までを丁寧に解説していきます。
あなたもWeb担当者になったつもりで話を読み進めていってください。
この講義を終えた頃には、あなたのまわりで、きっとあなた以上にSEO対策に詳しい人はいなくなるはずですよ。
SEO対策まとめ

それでは早速、SEO対策の講義をはじめていきます。
今回お話しするのは、大きく分けて「基本」と「応用」の2つです。
「基本」「応用」では、
それぞれ以下内容についてお話しする予定です。
【基本編】
- SEO対策の意味を理解しよう
- なぜSEO対策に力を入れるべきなのか?
- SEO対策には公式マニュアルが存在する?
- 内部対策と外部対策について理解しよう
- relevance(関連性)について理解しよう
- ユーザーインテント(検索意図)をおろそかにするとスベる
- すべてはインデックスから始まる
- ツールを活用しよう
- タイトル(title)について考えてみよう
- ディスクリプション(description)にも気をつかってみよう
- 競合調査の作法
- ブログで集客してみよう
- Webライティングの作法
【応用編】
- コーディングチェックポイント
- ローカルSEO対策を理解しよう
- SEO対策の外注もあり
少し内容が多いので、一度ですべてを理解しようとせずに、少しずつ進んでくださいね。
【基本編】SEO対策
それではSEO対策基本編を学んでいきましょう。
基本的な内容ですが、
どれも非常に重要なものをピックアップしました。
SEO対策の意味を理解しよう
 新人Web担当
新人Web担当「SEO対策をして、うちのホームページを上位にしてほしい」と上司から依頼されています。SEO対策を使えば可能なのでしょうか?
 青山
青山SEO対策を使えば、ホームページの検索順位をあげることは可能です。ただ、勘違いしないでいただきたいのは、「SEO対策は魔法ではない」ということです。まずはSEO対策とは何かを理解しましょう。
SEOとは、「Search Engine Optimization(サーチエンジンオプティマイゼーション)」の略語です。
日本語では、
「検索エンジン最適化」と呼ばれています。
検索エンジンというのは、検索のためのシステム・プログラムのことです。
 青山
青山普段スマホやパソコンで何かを検索するときに検索エンジンを使っていると思います。
 新人Web担当
新人Web担当「Google」とかのことですか?
 青山
青山そうです。「Google」も検索エンジンのひとつです。ほかにもMicrosoftの「Bing」などもあります。
「検索エンジン最適化」とは、ホームページやブログを、「Google」や「Bing」に対して最適化することを意味します。
ポイントは「最適化」という言葉で、「1位にする」とか「上位表示する」とかいった意味ではないという点です。
「SEO対策=上位表示のためにやること」というイメージが定着していますが、本来は、検索エンジンに対して「最適化すること=評価されやすい状態にすること」こそがSEO対策です。
ですので、SEO対策を行ったからといって、必ず上位表示ができるわけではないです。
この点を勘違いしてしまうと、仮にSEO業者に仕事を依頼した際に、後々トラブルになってしまう可能性があります。
とは言いつつ、誰かがSEO対策と言う場合、それは上位表示のための施策のことを指していることが多いです。
この場でも、「SEO対策=上位表示のための施策」として取り扱っていきます。
ただ、SEOとは検索エンジン最適化のことであって、魔法のような方法を使って上位表示することではないという点を頭の片隅に置いておいてください。

なぜSEO対策に力を入れるべきなのか?
 新人Web担当
新人Web担当SEO対策に力を入れるという会社の方針は間違っていませんか?
 青山
青山はい、間違っていないです。SEO対策を行うと、検索順位が改善される可能性が高く、検索順位が改善されることによって、アクセス数が増加し、結果的に売上増加につながる可能性があります。
 新人Web担当
新人Web担当そうなんですね、よかったです。社内で、SEO対策に力を入れた方が良いという声のほかに、意味がないという声もあったので心配でした。
 青山
青山「SEO対策には意味がない」と言う人たちもいます。そういう人たちはたいていの場合、自分で試したことがないため、どこかの誰かが言っていたことを真に受けているか、間違ったSEO対策を過去に行なって失敗したといったケースが多いと思います。
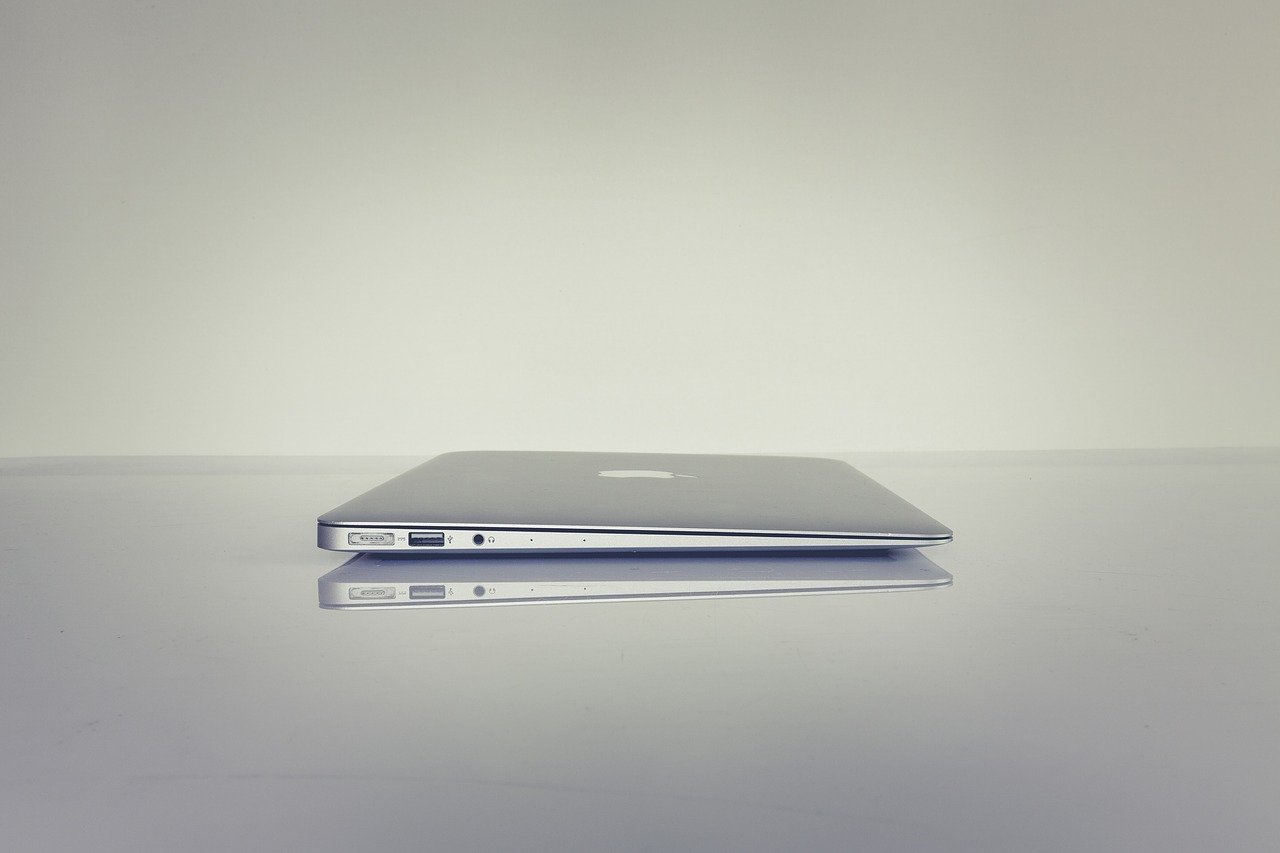
SEO対策には公式マニュアルが存在する?
 青山
青山実はSEO対策には公式マニュアルのようなものが存在します。
 新人Web担当
新人Web担当えっ本当ですか?だったらそのマニュアル通りにやればOKじゃないですか?どこにありますか?早く教えてください。
 青山
青山「Google検索セントラル」というサイトです。Googleが公式に発信しているSEOの情報サイトです。
 新人Web担当
新人Web担当ありがとうございます。じゃあ「Google検索セントラル」を読んでその通りにやればSEO対策はバッチリということですか?
 青山
青山いや、「Google検索セントラル」の内容に一通り目を通すことは大事ですし、「Google検索セントラル」の内容に沿ってSEO対策を行う必要もありますが、「Google検索セントラル」の内容はあくまでも基本的な内容です。
 新人Web担当
新人Web担当それはつまりどういう意味でしょうか?
 青山
青山「Google検索セントラル」通りにSEO対策を行なって上位表示できるなら、きっとみんなが一斉にやるので結局効果がなくなります。また、その通りにやれば上位表示できるのであれば、「Google検索セントラル」に検索アルゴリズムの答えが掲載されていることになります。そんなはずないですよね。
 新人Web担当
新人Web担当まぁそれはそうですね。
 青山
青山「Google検索セントラル」に掲載されているのは、あくまでもSEOの基礎的な内容や「これはやったらダメだよ」といったガイドラインです。たとえばゲームの説明書だって、それを読んだからといってクリアできるわけではないですよね。でも基本的な操作を知るためには役に立ちます。それと同じです。
SEO対策に力を入れる場合には、「Google検索セントラル」の内容には必ず目を通しておきましょう。
「Google検索セントラル」では、「品質に関するガイドライン」や「robots.txtの設置方法」「構造化データの種類」などをはじめとした、技術的な内容を学ぶことができます。
とくに技術的な内容についてはGoogle公式のため信頼性抜群です。
応用レベルのSEO対策を実施する場合には必ず目を通すことになると思うので、お気に入り登録しておきましょう。

内部対策と外部対策について理解しよう
 青山
青山まずは「内部対策」と「外部対策」について学びましょう。
 新人Web担当
新人Web担当はい、よろしくお願いします。
 青山
青山SEO対策には、大きく2種類「内部対策」と「外部対策」があります。
内部対策とは、ホームページのHTMLソースやプログラムの改修を行うことです。
外部対策とは、ホームページの外部の対策、つまり被リンク対策のことです。
 青山
青山かつてはSEO対策と言えば外部対策(被リンク対策)のことでしたが、評価基準の変更によって、最近では被リンク対策の重要性は薄まりつつあります。
 新人Web担当
新人Web担当では内部対策に力を入れた方が良いということですか?
 青山
青山はい、内部対策に力を入れた方が良いです。今でも被リンクの効果はありますが、場合によっては逆効果になるケースもあるため、まずは内部対策に力を入れましょう。被リンクについては、あくまでも自然なリンクの獲得を目指していきましょう。


relevance(関連性)について理解しよう
 青山
青山次はrelevance(関連性)についてです。relevance(関連性)はSEOの基本中の基本です。しっかりと理解しましょう。
 新人Web担当
新人Web担当なんか難しそうな言葉ですね。
 青山
青山でも意味はシンプルですよ。簡単に言うと、検索エンジンは検索された言葉とページとの関連性を考えてページを表示するということです。
 新人Web担当
新人Web担当「レッサーパンダ」と検索した場合、「レッサーパンダ」について書かれたページが表示されるということですよね?
 青山
青山その通りです。なぜレッサーパンダなのか謎ですが、まぁそれはおいておいて。だからあるキーワードで検索結果に表示させようと思ったら、そのキーワードについてのページを作る必要があるということです。
 新人Web担当
新人Web担当「レッサーパンダ」が好きなんです。なんか当たり前のことを言っているような気もしないでもないですが、わかりました。
 青山
青山当たり前のことですが、意外に理解できていない人もいます。SEO対策の基本中の基本なので、しっかりと覚えておきましょう。

ユーザーインテント(検索意図)をおろそかにするとスベる
 青山
青山relevance(関連性)に続いて、ユーザーインテント(検索意図)も重要なので理解しましょう。
 新人Web担当
新人Web担当また難しそうな言葉が出てきましたね。
 青山
青山ユーザーインテント(検索意図)も意味自体は簡単です。ユーザーが検索する意図、つまり検索の目的を考えるということです。
 新人Web担当
新人Web担当検索の目的ですか?
 青山
青山はい、検索する人には、必ず検索の目的があります。たとえば「ジャガイモ レシピ」と検索する人は、「ジャガイモを使った料理を作りたい」人です。
 新人Web担当
新人Web担当そういう意味ですね。でもそれの何が重要なのですか?
 青山
青山ユーザーの検索の目的をきちんと考えてから記事を書いたり、コンテンツを作ったりしないと、ユーザーの検索目的とズレたページを作ってしまう可能性があります。でもマッチしたページを作ることができれば、ユーザーが満足してくれる可能性が高くなります。
 新人Web担当
新人Web担当そういういうことですね。でも検索ユーザーの気持ちってどうやって考えれば良いのでしょうか?
 青山
青山実際に検索したり、SNSやお悩みサイトでリサーチしたりと、方法はたくさんあります。

すべてはインデックスから始まる
 青山
青山次は非常に重要なトピックです。「SEOのはじまりはインデックス」と言っても過言ではないほどに、インデックスは重要です。
 新人Web担当
新人Web担当インデックスって何ですか?
 青山
青山インデックスとは、検索エンジンのデータベースにページが登録されることを意味します。
 新人Web担当
新人Web担当登録ですか。データベースに登録されるのって、そんなに大事なことなのですか?
 青山
青山はい、非常に大事です。検索したときにページが表示されるのは、そのページがデータベースに登録されているからです。逆に、登録されていないと、検索されてもページが検索結果に表示されません。
 新人Web担当
新人Web担当えっ、それじゃ、登録されていなかったら大変ですね。
 青山
青山はい、登録されていなかったらかなりまずい状態です。インデックス登録されてないという相談は意外に多いので、気をつける必要があります。
インデックスについては必須で学ぶ必要があります。
理由は上で挙げた通り、インデックスされていないと検索結果に表示されないからです。
ページがGoogleのデータベースに登録されているかどうかは、以下のように検索に入力していただければわかります。
site:調べたいページのURL
例)site:https://marketing-planner.com/
「site」で検索して、検索結果に表示された場合、データベースに登録されています。
登録されていない場合には、何らかのトラブルが発生している可能性があるため、対処が必要です。


ツールを活用しよう
世の中にはSEOに役立つツールがたくさんあります。
ツールはあくまでもヒントを与えてくれるだけなので、ツールにすべてを任せることはできません。
けれどもツールを活用することで、作業の効率化につながったり、自分では思いつかなかった施策が見つかったりと、良いことがたくさんあることはたしかです。
ですので積極的にツールを活用していきましょう。
とくに、以下ツールはサイト公開時に登録必須です。
- Googleサーチコンソール
- Googleアナリティクス


また、「Chromeの拡張機能」には、SEO対策に使えるツールがたくさんあります。
以下記事を参考に、必要に応じて導入してください。

タイトル(title)について考えてみよう
 青山
青山タイトル(title)は非常に重要な意味を持った要素です。ですので、タイトルの付け方をしっかりと学びましょう。
 新人Web担当
新人Web担当なぜタイトル(title)は重要なのですか?
 青山
青山タイトル(title)が、検索順位を決める要素の中でも大きな影響を持つと考えられているためです。実際、タイトルを変更することで順位が変動するケースが多いため、重要な要素であることは間違いないです。
 新人Web担当
新人Web担当そういうことですね。タイトルを決めるときのコツはありますか?
 青山
青山はい、まず前提として、ページの中身を的確に表したものである必要があります。希望するキーワードで検索順位をあげたいからといって、ページの中身とまったく別のものにするのはNGです。
 新人Web担当
新人Web担当わかりました。文字数に決まりはありますか?
 青山
青山明確に何文字と指定されているわけではありませんが、30文字程度が推奨されています。あまりにも長いと、検索結果で省略されてしまうためです。
 新人Web担当
新人Web担当わかりました。他には意識するポイントはありますか?
 青山
青山上位表示を狙いたいキーワードを必ず含める必要があります。あとは、クリックしたくなるような文章にするのも大事です。
 新人Web担当
新人Web担当ありがとうございます。タイトルを工夫してみます。
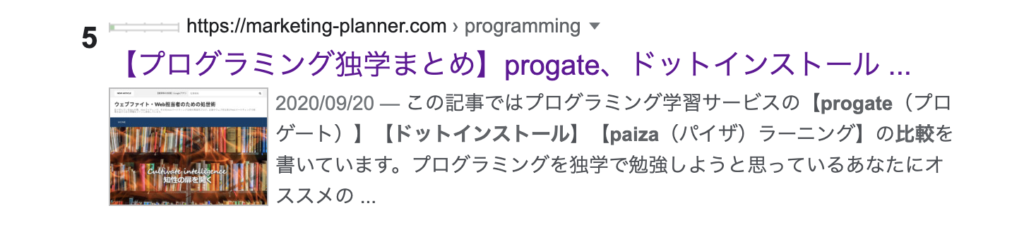
タイトルは検索結果の見出しとして表示されます。
上記画像の【プログラミング独学まとめ」】〜の箇所がタイトルにあたります。

ディスクリプション(description)にも気をつかってみよう
 青山
青山タイトルと同じようにディスクリプション(description)も工夫して付けてみましょう。
 新人Web担当
新人Web担当すみません、ディスクリプションって何ですか?
 青山
青山検索結果のタイトルの下に表示される概要文のことです。
 新人Web担当
新人Web担当ディスクリプションも検索順位をあげるために重要なのですか?
 青山
青山いや、ディスクリプションにSEO効果はないと言われています。
 新人Web担当
新人Web担当ではなぜディスクリプションに力を入れる必要があるのですか?
 青山
青山ディスクリプションがクリック率に影響を与えるからです。ディスクリプションを読めば、なんとなくページの中身を想像できるため、クリック率に影響を与えます。
 新人Web担当
新人Web担当言われてみれば、概要文を読んでクリックしたり、しなかったりすることはあります。
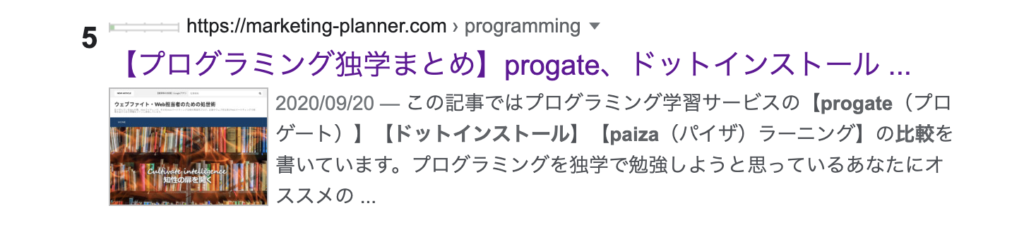
ディスクリプションは検索結果の見出しの下に表示されます。
上記画像の「この記事ではプログラミング学習サービスの〜」の箇所がディスクリプションにあたります。
ディスクリプションの設定方法は以下です。
- 上位表示を狙うキーワードを含める
- 文字数は120文字程度でまとめる
- クリックしたくなるような文章を考える

競合調査の作法
 青山
青山SEO対策の基本として、「競合調査」の方法も学んでおきましょう。
 新人Web担当
新人Web担当うちの会社にも競合がいます。上司が「競合サイトには勝ちたい」と言っていました。
 青山
青山競合について考えるときの注意点は、必ずしも今把握している競合だけが競合になるとは限らないということです。
 新人Web担当
新人Web担当どういうことですか?
 青山
青山たとえば美容室があったとしましょう。その美容室のオーナーは近隣の美容室のことを競合と思っているかもしれませんが、ネットで検索した際に他にもたくさん美容室が表示されていたら、そのすべてが競合になり得ます。
 新人Web担当
新人Web担当なるほど、そういうことですね。うちの会社も、他にも競合がいないチェックしてみます。

ブログで集客してみよう
 新人Web担当
新人Web担当「SEOのためにブログをはじめるべき」という声が社内であがっています。ブログって有効ですか?
 青山
青山はい、ブログは非常に有効です。
 新人Web担当
新人Web担当でもブログって、「今日はランチに何食べました」とか、そういう日記みたいなものですよね?
 青山
青山いや、日記のような記事を書いてしまうと逆効果になってしまいます。
 新人Web担当
新人Web担当えっ、そうなんですか。社内の人たちは「好きなラーメン店でも順番に書いていこうか」とか盛り上がっていましたが。
 青山
青山ブログを書く意味のひとつは、検索流入の窓口を増やすことです。ブログの記事を読んだ人たちに、会社や商品のことを知ってもらうことが目的のはずです。需要のあることを書かないと、せっかくブログに来てくれても、会社や商品を知ろうとは思ってもらえませんよ。
 新人Web担当
新人Web担当たしかに、それはそうですね。では何を書いたらよいでしょうか?
 青山
青山業界や会社に関係のあることで、あなたが知っていて読者は知らないことをテーマにするのがオススメです。
 新人Web担当
新人Web担当自分が知っていて、読者が知らないことですか?
 青山
青山たとえば、私はSEO対策の情報を自分のブログで発信しています。SEO対策をはじめたばかりの人にとってはどれも役に立つ情報ばかりを発信していますが、業界的には誰もが知る当たり前の情報が多いです。
 新人Web担当
新人Web担当なるほど、その業界にいない人にとっては知らない情報ということですね。何となくわかりました。ブログも頑張ってみます。
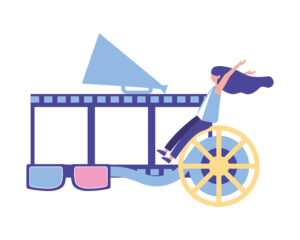
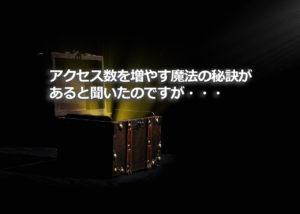
Webライティングの作法
 青山
青山ブログついでに話しておくと、SEO対策やインターネットで商品を売るためには、Webライティングは避けて通れない分野です。
 新人Web担当
新人Web担当Webライティングって文章術のことですか?
 青山
青山はい、Webに特化した文章術のことです。Webコンテンツの多くは文章でできています。ですので、結果を出そうと思ったら文章について学ぶ必要があります。
 新人Web担当
新人Web担当でも文章って苦手です。
 青山
青山難しく考える必要はありません。文章は文字を使った人とのコミュニケーションです。リアルの場で人と会話するのとそれほど変わりません。
 新人Web担当
新人Web担当そういうものでしょうか。でも文章をスラスラ書ける気がしないです。
 青山
青山Webライティングはスキルの一種なので、すぐに上達するものではありません。けれども、日々ブログを書いたり、トレーニングを行ったりすれば、必ず上達します。
ブログ(コラム)記事を書いたり、商品ページを作ったりする場合、必ず文章を書く必要があります。
ですので、Webライティングのスキルがあった方が良いです。
記事については外注するという選択肢もあるため、必ずしも自分が書く必要はありませんが、それでも、納品された記事が問題ないかどうか、その記事が成果を出せるかどうかは、Webライティングの知識・スキルがあった方が判断しやすいです。
ライターでないなら、極めるほど学ぶ必要はありませんが、基礎的なスキル・知識は習得しておきましょう。
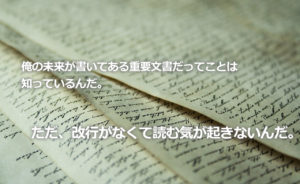

【応用編】SEO対策
基本編の内容を理解できれば、一般的な企業であれば、「元SEO会社の社員」がいるとかでない限り、「自分よりもSEOについて詳しい人はいない」という状態になると思います。
ただ、基本編だけでは、競合サイトの多い業界の場合には、上位表示は難しいです。
競合が多い業界の場合、Webマーケティングに大金をかけていたり、SEO会社が入っているケースが多いです。
こういったケースで競合と対等に戦おうとする場合、こちらも、お金を使うとか、人手を使うとか、何らかの工夫が必要です。
また、SEO対策に力を入れていく場合、必然的にプログラミングの知識やスキルも必要になってきます。
たとえば、SEO施策の「構造化マークアップ」や「ページスピードの改善」などを行う場合、プログラミングの知識、スキルなしでは不可能です。
必ずしも自分がやらなければならないわけではありませんが、社内の誰かや依頼先(外注)が必要になります。
ご自身で頑張りたいという場合、当サイトではプログラミングに関する情報も公開しているので、できそうかという点含め、お読みいただければと思います。

コーディングチェックポイント
 新人Web担当
新人Web担当SEO対策に力を入れるなら、プログラミングもできるようになった方が良いですか?
 青山
青山はい、プログラミングの知識・スキルがあると、できることが増えます。
 新人Web担当
新人Web担当でも、プログラミングって難しそうです
 青山
青山ここで0からプログラミングについて語ることはできないので、SEOのために最低限知っておきたいことをお話しします。
SEO対策に関係するプログラミング言語は、たとえば以下です。
- HTML
- CSS
- PHP
- JavaScript
- SQL
この中でも、最低限の内容を理解しておいた方が良いのはHTMLです。
※HTMLは厳密にはプログラミング言語ではなく、マークアップ言語です。
なぜHTMLを理解しておいた方が良いのかというと、多くのホームページがHTML言語で作られているからです。
また、SEOで重要な意味を持つ<title>や<meta>タグなども、HTMLで書かれています。
ですので、HTMLを理解できるようになっておく便利です。
逆に、HTMLを理解できないと、重大なミスがあるホームページが納品された場合であっても、対処できません。
必ずしも自分で対処する必要はないかもしれませんが、最低限エラーを発見できるようにはなっておきたいです。
確認したい点は、
具体的には以下のような点です。
- HTMLにエラーがないか
- 不必要なメタタグが設定されていないか
- <title>や<description>がちゃんと設定されているか
- h1タグが存在するか
「W3C Markup validation Service」を使えば、HTMLのエラーチェックができます。
サイトにアクセスして、調べたいサイトのURLを入れるだけです。

「不必要なメタタグ」とは、
noindexタグのようなタグです。
noindexタグが設定されていると、
ページがGoogleに登録されません。
意図的に設定しているなら問題ありませんが、意図せず設定されてしまっているなら、大きな問題です。
万が一設定されている場合には、
すぐに対処が必要です。
<title>や<description>については、「タイトル(title)について考えてみよう」「ディスクリプション(description)にも気をつかってみよう」の項目で解説しているので、そちらをご覧ください。
h1タグをはじめとした見出しタグについても、HTML言語で書かれています。
<title>や<description>と同じくチェックできるようにしておきましょう。

ローカルSEO対策を理解しよう
 新人Web担当
新人Web担当ローカルSEO対策って何ですか?
 青山
青山ローカルSEO対策とは、地域性の強いキーワードのSEO対策を行うことです。
たとえば、美容室を例にしましょう。
美容室を探すときって、「美容室」とそのまま検索することもあれば、「○○(地域名)+美容室」で検索することもありますよね。
地域名を入れずに検索した場合には、位置情報をもとに、近くの美容室の情報を表示する仕様になっています。
このように、地域名に関わるようなキーワードで検索された際に、上位表示を目指すのがローカルSEO対策です。
もしもあなたが美容室のオーナーだったとしましょう。
髪を切りたいと思っている見込み客が「○○駅+美容室」とGoogleで検索したとします。
仮に、あなたの美容室のホームページが表示されていないのにもかかわらず、競合の美容室のホームページが表示されていたとします。
この場合、見込みのお客さんは、競合のホームページのみを見て、美容室を決めてしまうかもしれません。
逆に、あなたのお店のホームページが上位に表示されていたとしたらどうでしょうか。
検索した見込み客の多くが、あなたのお店のホームページを目にすることになります。
その結果、お店に来てくれるお客さんは増えるはずです。
ローカルSEO対策は、実店舗を持っているビジネスにとっては大きな効果を発揮します。
ですので、実店舗のあるビジネスの場合には、対策必須です。
具体的には以下対策を行います。
- Googleマイビジネスの活用
- Webサイトのアクセス情報を充実させる(地域に関わるキーワードを入れる)


SEO対策の外注もあり
競合サイトが多い場合や、競合サイトがWebマーケティングに力を入れている場合には、外注も選択肢のひとつです。
「施策の案出し」から「コンテンツ作成」「プログラム修正」などを、社内ですべて完結できる場合には問題ありませんが、そうでない場合には、プロに依頼した方が効率的なケースもあります。
SEO対策のサービスは、月数千円のものから数十万円のものまで幅広くあります。
外部対策(被リンク対策)中心の会社があれば、コンテンツ作成に強い会社や、プログラム改修に強い会社など、会社によって強みが異なります。
どの会社に依頼するべきかは実際にサービス説明を受けてみないとわかりませんが、一つ確実に言えることは、よくわからない被リンクサービスを提供している会社との契約はやめた方がよいということです。
質の悪いリンクがあっても評価されませんし、質の悪いリンクを提供している会社の場合、契約のトラブルなど、面倒なトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
また、費用を抑えたい気持ちは誰にもあると思いますが、あまりにも低価格すぎるサービスも考える必要があります。
料金が高いからといって必ずしも上位表示できるとは限りませんが、高いサービスにはそれなりの理由があります。
また、
安いサービスにもそれなりの理由があります。
SEO会社に依頼する場合には、きちんと営業担当の話を聞いて納得できる会社を選びましょう。



SEO対策その後
 新人Web担当
新人Web担当ホームページからの売上があがってきているので、別店舗のホームページのSEO対策も依頼されました。大変だけど、なんか仕事が楽しいです。
 青山
青山Webマーケティングの必要性は年々高まってきていますが、まだまだWebマーケティングでしっかりと成果を出せる人材は足りていません。ですから、SEO対策の知識やスキルがあると、WEBに力を入れている企業で重宝されますよ。
 新人Web担当
新人Web担当はい、SEO対策を学んでよかったです。SEO対策って、抽象的でわかづらいものだと思っていたのですが、実はシンプルで、当たり前のことをやっていたのですね。
 青山
青山はい、その通りです。検索ユーザーに求められている答えを適切な形で提示してあげれば、上位表示することはそんなに難しいことではありません。
 新人Web担当
新人Web担当これからもSEO対策を学び続けていきます。けど今回の講義でWebマーケティングの楽しさに気づいて、Web広告とかSNSにも挑戦してみたいと思い始めています。
 青山
青山ぜひ挑戦してみてください。SEO対策はあくまでも施策のひとつでしかありません。Web広告やSNSを活用すれば、もっと集客ができるし、活躍の場も広がりますよ。それでは頑張ってください。
 新人Web担当
新人Web担当はい、頑張ります。
ここで挙げたSEOの話は、SEOのほんの一部分でしかなく、実はまだまだ奥が深いです。
ですから、もしもあなたがもっともっとSEOについて知りたいとお考えでしたら、これからもずっと学び続けることができます。
私自身、これから先も学び続けるつもりです。
本当はもっともっとたくさん伝えたいことがありますが、ひとまず今回の講義はこれで終了です。
この記事があなたのWebサイトやブログに良い影響を与えることを心より願っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
