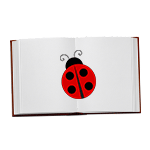「家にいよう」で社会は二分化された。
今いる場所で生きることを考える。今を楽しく生きていく方法を考える
私の好きなドラマ『ロングラブレター~漂流教室~』のメッセージは、「今を生きろ」でした。
「見たことがない」という方のためにドラマの内容をざっくりご説明すると、『ロングラブレター』は、ある高校の生徒・教師らが校舎ごと未来にタイムスリップしてしまうという話です。
タイムスリップというと、なんだか楽しそうな雰囲気満載ですが、高校生らがタイムスリップした未来は、人類滅亡寸前の未来でした。
人類滅亡寸前の未来で、高校生数十人と大人数人は生きていかなければならなくなったのです。
はじめは誰もが、「意味がわからない」と状況を理解できずにいますが、徐々に状況を把握していくと、パニックで頭がおかしくなる人たちと、少しだけ現実を受け入れて、それでも生きいこうという人たちとに分かれていきます。
物語の終盤になると、誰もが前を向き始め、置かれた場所で生きることの意味を理解していきます。「今を生きろ」というメッセージは、置かれた場所で精一杯生きるための指針となる言葉でした。
今、たくさんの悲しいニュースが入ってきていると思います。目を背けたいことがたくさんあると思います。
そして、悲しいニュースは他人事ではなくて、「いつ自分が当事者に・・・」といった恐怖もあると思います。
おまけに、マスクどころか、いろいろなものが買えない、しかも家から出られないという、不自由な生活を強いられています。
だから多くの人たちが今、
すごく苦しい思いをしていると思います。
今って至る所で「自粛自粛」って、なんか「いいから耐えろ」みたいな圧力が感じられますが、なんかそういう表現は私はあまり好きではなくて、もっと今この世界を楽しく生きていく方法もあるのではないかと思っています。
ただ、今こんな状況であっても、できることは必ずあるし、というか、今だからこそできることがたくさんあるし、そしてこんな状況であっても楽しく生きていくことは可能だと、私は思っています。
こんなことを言うと、場合によっては、「大変な人もいるんだぞ」と怒られるのかもしれません。でも暗い雰囲気だからといって、暗く生きる意味がわからないと言いますか、少なくとも私は、今この時を楽しく生きたいと思っていますし、チャンスだとも考えています。
たとえば、今外出できないこの時間を全て読書にあてたらどうでしょうか?
何冊くらいの本が読めそうですか?
たとえば、今テレワークができないと嘆いてる人も、休日の家で勉強や業界研究をしたら、数か月後にはテレワークができる業界に転職できると思いませんか?
この状況がどのくらい続くかわからない今なのだから、今この瞬間が「もう遅い」とは言えないと思います。
私の言っていることは所詮「綺麗ごと」かもしれませんが、「今できることを大切にする」ということは、間違っていないんじゃないかと思います。
たしかに、今の世界はひどい。鎖国状態だし、毎日暗いニュースばかり流れてくる。

個人個人が苦しい時期って、
どんな時代でも全然珍しくないですよね。
いつだって借金を背負っている人はいるし、うつ病で苦しんでいる人はいます。
私自身のことを振り返ってみても、人生において辛い時期というのはたくさんありました。
たとえば毎日のように面接に落ちる日々だったり・・・
たとえば貯金が底をつきそうな日々だったり・・・
私自身が辛い時期というのはたくさんありましたが、でもそんな時でも、世界はいつも元気でした。あなたが苦しい時も、きっと世界は無関係に微笑んでいましたよね。
「今年の夏のボーナスは・・・」とか、「ある映画の興行収入が歴代一位に輝いた」とか、自分がどれだけ落ちぶれても、世界はいつだってどこ吹く風で、景気のいい話で溢れていました。
個人は頻繁に落ちぶれたりしますが、世界中がヤバイ時期というのは、数えられるレベルでしかなかったと思います。
ところが今は、
世界という大きな存在そのものがコロナ危機で苦しんでいます。
思い返せば、ヤバいなと思う時期もありましたね・・・

過去を振り返れば、日本中や世界中が大変な時期もたしかにありました。
私が生まれる前まで遡れば、今とは比べものにならないくらいの危機だってあったでしょう。
私が生きている間でも、たとえば、東日本大震災やアメリカの同時多発テロ事件、経済に打撃を与えたリーマンショックなどがありました。
思えば東日本大震災が起きた当時、テレビは地震や津波を伝える報道で一色になりましたね。
原子力発電所の爆発によって、「どうやら日本が危ないらしい」という声が広がり、日本から非難する外国人、日本人の中にも、少しでも東北から離れようとする人たちがいました。
そういえば、バイト先の外国の方はバックレましたね。その穴埋めをしたような気がします。
そう、それと、
「ポポポポーン」が懐かしいですね。
その当時も私は、今と同じように毎日インターネットばかり見ていた気がします。
「日本はヤバイ」という人たちがいて、一方で関係なく遊び歩く人たちがいて、「バカだ」と言う人たちがいて、「バカだ」と言われても折れない人たちがいて、今と同じですね。
あとは、そう、電力供給の関係で夜の店が閉店時間を早めていたような。
そういえば、
あの頃も、世間は「自粛」という言葉を使っていた気がします。
あぁ、
思い返せば、大変な時期もありましたね。
ただ、今回の件と過去の件が決定的に違うことは、今回の件が、個人や日本だけでなく、「世界中が苦しんでいる」という点です。
これまでの問題なら、ある会社が嫌だったら別の会社に転職するとか、日本が危なくなったら海外に行くとかもできましたが、今は非常に身動きが取りづらい状態です。
海外では「今は戦争中だ」と言われたりしていますが、たしかにこれはある意味で、比喩的な意味でなくとも戦時中のような状態なのかもしれないと感じたりします。
そう、小さなことかもしれないけれど、トイレットペーパーが買えませんでした。
トイレットペーパーを探し回って、ドラッグストアを6軒まわりました。
そしてその日私は、
トイレットペーパーを買えませんでした。
お金はある。
お金はあるんです。
過去には「トイレットペーパーを買うのももったいない」というような時期もありましたが、今はちゃんと働いていて、トイレットペーパーくらいなら余裕で買えます。持てるものならまとめて買ってしまってもいいんです。
だけど、
余裕で買えても売ってくれない。
「入荷なし」の貼り紙だけが寂しく揺れている。どこもそんなかんじ、売っている場所がない。
もしもタイムマシンがあって、そのタイムマシンに乗って過去の自分に会いに行ったとして、
「トイレットペーパーが買えなくなるぜ」という話を自分にしたら、自分は信じてくれるだろうか?
いや、信じるかもしれません。
信じやすい性格ですし。
まぁそれはどうでもいいですね。
日本の政府は今回の件を「歴史的緊急事態」として記録していますが、朝起きるとたまに「本当にこれは現実なのか?」と思うこともあります。
だけど、ある意味今の生活は望んでいた生活でもある

ですが正直なところ、
私は今の生活に特別文句はありません。
買えない物があることと、スーパーにすら気軽に行けないことを除いて、ですが。そして、「少なくとも今のところは」と付け加えておく必要もありますが。
外に出れないということ自体は、全く苦でないというか、むしろ出たくないと常々思っていたので、ある意味、理想の生活とも言えるわけです。
でもなぜか、
しっくりこないんです。
その理由を考えてみた時に、
ごく当たり前の話をすれば以下のような点からです。
- カフェに行けない
- 本屋に行けない
- 旅行に行けない
カフェに関しては、自宅での環境を整えたので、「まぁいいか」とも思うのですが、本屋に行けないのは辛いですね。
「まぁAmazonや楽天ブックで買えばいいか」とも思うのですが、皆が同じことを考えるので、「品切れ中」になりがちですし、ネットの本販売は、配達中に本の端が折れたりするから嫌なんですよね。細かい所ですが。
梱包しっかりしているパターンの時と「テキトーに封筒に入れたんじゃね?」パターンがあって、後者の場合、「よく折れないで我が家にやってきたな」と開封後に本を褒めたくなるくらい、ただ封筒に本が入れられてるだけなんですよね。気にし過ぎですね。
あとは毎週本屋で最新刊をチェックするというのができなくなりましたし、美人な書店員に会計してもらうこともできなくなりました。
旅行に行けないというのも大きいですね。
「次飛行機乗れるのいつなんだろう?」と切実に思います。航空会社も世界中でつぶれるでしょうね。まぁただ国が介入するので飛行機がなくなることはありませんが。
というのが現実的な理由ですが、
もう少し感情的に表現してみると以下のようなかんじです。
- 子どもが公園ではしゃいでいないと意味がない
- 高校生カップルが電車の中でイチャイチャしていなければ意味がない
- 祭り中で頭に鉢巻の中年オヤジが「スーパードライ」を片手に持っていないと意味がない
- 「モデルか?」と思うほどの美人が歌舞伎町を歩いていないと意味がない
- 「頭悪そうだな~」と思うような大学生カップルがおそろいのスウェットでドンキに買い物に来ていなと意味がない
こういう、ミスチルが歌うところの「スパイス」のようなものが自分の世界からなくなってしまっているような気がしてなりません。
- 財布に2,000円しか入っていないのに高級時計売り場で時計を眺めたり
- 何一つとして用がないのに夜の池袋西口公園のベンチに座ったり
- 店員に声を掛けられるのが嫌だからイヤホンをしながら少し遠めでMacBookを眺めたり
- 「もう二日酔いはこりごり」と思っていたのにクラブでテキーラを飲んでしまったり
要するには、私の人生はお偉い方が言うような「不要不急」や「アンチ・ソーシャルディスタンス」で成り立っていたんじゃないかと、今を持って気付きました。
人生から「不要不急」をなくした結果どうなったか?
たしかに、悪くはありません。
仕事や勉強が効率的に進みます。
お金が減らないからお金が貯まります。
だけど何かが違う・・・
今の快適な状態って、なんかのび太が「どくさいスイッチ」を使って皆を世界から消しちゃったときのような感覚です。
この問題を解決する答えはあるのかを考えてみる

「じゃあどうすればいいのか?」となった時に、「以前の生活に戻るためにはどうすればいいのか?」ということをよく考えたりもします。
ただ、おそらくもう、
完全に元の状態には戻れません。
誰もがリスクがあることを知ってしまったからです。
- 対面で仕事をするということのリスク
- 外国と取引するということのリスク
- 雇用されるということのリスク
- 雇用するということのリスク
- 人と接することのリスク
- 人と接しないことのリスク
表面上は元通りになったとしても、
それは必ずしも元の通りではありません。
だからこそ、
新しい生き方が必要になります。
この問題の専門家は世界に誰もいない
毎日毎日たくさんの意見が飛び交っています。
感染症の専門家の方や、医療関係者、政府関係者、何かと口を突っ込みたがる有名人。そしてコウモリのように片っ端から音を拾って発信するマスメディア。
ただ私たちが考えなければいけないことは、この問題はとうに一人の専門家がカバーできる域を超えているということです。ある人は、一方で専門家であり、もう一方で素人以下だったりするということを理解しなければなりません。
たとえば医者は身体の症状の診断結果をくだせるかもしれませんが、これから先いつ会えるかわからない遠距離の恋人たちの寂しさを癒してあげることはできません。
たとえば感染症の専門家は感染症についての知見はありますが、たとえば「来月の従業員の給料をどうしようか?」と苦しむ経営者の資金繰りを解決することはできません。
一方で専門家であり、もう一方で素人以下の人たちが、四方八方で好き勝手言っているのが今の状況なのです。
皆がそれぞれ色々な立場から物を言っていて、それぞれが守るべきものも違うから、一ヶ月引きこもっている人がいる一方で、出稼ぎで水商売とかやっている人たちがいるというおかしな状況になっているのです。
つまるところ、テレビのニュースやインターネット、国会の場で争われているのは、それぞれの正義の話なのです。パチンコや水商売だってそうです。これもまた、ある面で戦争と同じです。
そんな世界でこれからどう生きていくのか

まず一つ考えなければいけないことは、これからの世界は二分化されていくということです。
以前からよく言われていたのは、「持てる者と持たざる者」、所謂経済的な格差社会ですね。
ユニクロの柳井氏がずっと前に、経済的な「中間層の減少」について言及し話題になりましたが、今回の危機によって、それまで当たり前に生活できていた人たちが、ほんの数ヶ月でどん底に落ちるケースというのが出てきています。それまで中間層だった人たちが、年収100万円レベルに落ちようとしています。
ではなぜ、それまでふつうに生活できていた人たちがほんの数ヶ月でどん底に落ちたのか?
それは、今回の危機が、人と人との接触リスクをもたらしたため、対面での仕事がしづらくなり、その結果解雇されたり、倒産につながったためです。
なぜ人と人との接触に関わる仕事をしている人たちが解雇されたり、経営が傾いたりしているのか?
一つの答えは、
【需要の減少】です。
治療薬もワクチンもない、感染後にどうなるかもわからない未知のウイルスに感染したい人なんていないので、「〇〇が危ない」となれば誰も近寄りたいとは思わなくなります。
スーパーなど日常生活に必須なものならまだしも、なくても生きられるものに関しては、需要が減少するのは当たり前のことです。
もう一つの答えは【自粛】です。
実際のところ、多くの企業が「緊急事態宣言」前までは営業をしていました。アルコールスプレーを置いたり、店員にマスクを義務化するなどして、営業を続けていました。
ところが、「緊急事態宣言」あたりから、飲食店をはじめとして、多くの企業が休業をはじめました。
自主的に休業を決めたところもあれば、「緊急事態宣言」による「休業要請」に従って仕方なく休業を決めたところもあります。
従業員を守るために休業を決めたところもあれば、需要の減少を理由に休業を決めたところもあります。
ところが一方で、「緊急事態宣言・休業要請」があったのちも休業しない企業もありました。
それはなぜでしょうか?
自分勝手だから?
経営者が強欲だから?
推測として、そのような考えを持つことも可能です。
たとえば少し視点をうつして、
次の2点について考えてみましょう。
- 「緊急事態宣言」後も公園で遊ぶ親子を想像してみましょう。
- ス―パーでマスクをせずに買い物をする背骨の曲がったおばあちゃんを想像してみましょう。
あなたはなぜ、「緊急事態宣言」後も親子は公園で遊んでいるのかがわかりますか?
あなたはなぜ、背骨の曲がったおばあちゃんがス―パーでマスクをせずに買い物をしているのかがわかりますか?
インターネットを見れば、「商店街の人混みが相変わらず。これじゃ問題は解決しない」というような声が散見されます。
「なぜ彼らは外に出ているのか?」という問いに対して、あなたの中に、確固たる根拠で示される明確な答えはありますか?
たしかにふうつに考えたら、
「家にいよう」は至極まっとうな答えに聞こえます。
なぜなら、
「家にいれば安全だから」です。
それにもかかわらず、公園で遊ぶ人たちがいる、店を開ける人たちがいる。
それはなぜなのでしょうか?
「人間は機械じゃないから」
これは一つの答えでしょう。
「緊急事態宣言」後に風俗に行ってバッシングを受けた議員がいましたね。
理由はいくらでも述べられそうですが、私の中の答えの一つとして、「ノアの箱舟」的な考え方があります。
今、世界中のいたるところで「家にいよう」ということが叫ばれています。
その一方で、「経済がもたない。店舗家賃の支払いに猶予を」と叫ぶ人たちがいます。
GMOの熊谷さんが「テレワークでも業績に影響ない」と言う一方で、タリーズジャパン創業者の松田公太さんは「飲食店における家賃支払い猶予を求める法律整備」の必要性を訴えています。
「家にいよう。家でも快適に過ごせる」と言う会社員がいる一方で、出稼ぎホストが話題になりました。
なぜ、世の中は一致団結できないのか?
それは、各個人が「ノアの箱舟に乗っているかどうか」によって、180度生き方を変えざるを得なくなっているからです。
これは少し恐ろしい表現ですが、「家にいよう。テレワークをしよう。自粛しよう」という考え方は、ある意味ノアの箱舟的な主張です。
「家にいよう。テレワークをしよう。自粛しよう」
これらの発言をしている人たちの立場を考えてみてください。
「家にいよう。テレワークをしよう。自粛しよう」
この条件であれば快適に過ごせる人たちがどんな人たちか考えてみてください。
今世界中の多くの場所で、舟に乗っている人たちと乗っていない人たちとの間で二分化が起きています。
これは、経済的な意味はもちろん、ライフスタイル的な意味も含みます。
何も考えていないような一部の例外の人たちを除けば、誰だって未知のウイルスには感染したくないはずです。
誰だって、「テレワーク快適~」とコーヒーを片手に仕事をしたいはずです。
誰だって「引きこもるって最高」と根暗な人のように生きたいはずです。引きこもりに関しては、少なくとも「今は」ですが。
でもそれができない人たちがいる。
それをしない人たちがいる。
なぜなら、彼らは「家にいよう」という旗が掲げられた箱舟に乗っていないからです。
そんな世界で、私たちはこれからどう生きていくのかを考えていく必要があるのです。
こういう世界では、
答えが一つだと思っていたら大やけどしますよ。
この記事の主題である「今いる場所で生きることを考える。今を楽しく生きていく方法を考える」という主張には、二分化する二つの立場の人たちそれぞれが考えるべきテーマが含まれています。
今、一方の立場の人たちは、
そこまで悪くない世界を生きています。
仕事があって、収入があって、身の安全をある程度保証されている。
そういう人たちが考える必要があるのは、「今を楽しく生きていく方法を考えること」かもしれません。
そしてもう一方の人たちは、
今、恐怖と不安の日々を生きていると思います。
仕事がなくなって、
収入の目処が立たなくなりそう。
あるいは、
仕事があっても、毎日人との接触がある。
そういう人たちが考える必要があるのは、「今いる場所で生きることを考える」ことだと思います。
- どうやって収入を確保するのか?
- 身の安全をどうやって守るのか?
それぞれ別の立場にいる人たちの声というのは届きづらいです。
人の数だけ意見はありますが、
それぞれの人たちにそれぞれの生活があります。
だから答えは自分で出す必要があります。
使命感をもって医療に従事する人たちがいる一方で、退職を選ぶ人たちもいます。スーパーやコンビのレジで働く人たちがいれば、命と時給の天秤の末に退職する人たちもいます。
東京での一人暮らし、バラ色の大学生活を夢見てたいたのもかかわらず、一人暮らしの家で孤独に泣いている人たちがいます。家族を守るために家に留まる人たちがいれば、今を大切にするために帰省する人たちもいます。
少なくとも私は、
そのどれもが答えだと思っています。
さいごのまとめになりますが、私は「家にいよう」に代わって、誰もに共通する言葉があったらいいなと思ったので書いておきます。
それは「未来はよくなると信じよう」という言葉です。
「未来はよくなると信じよう」
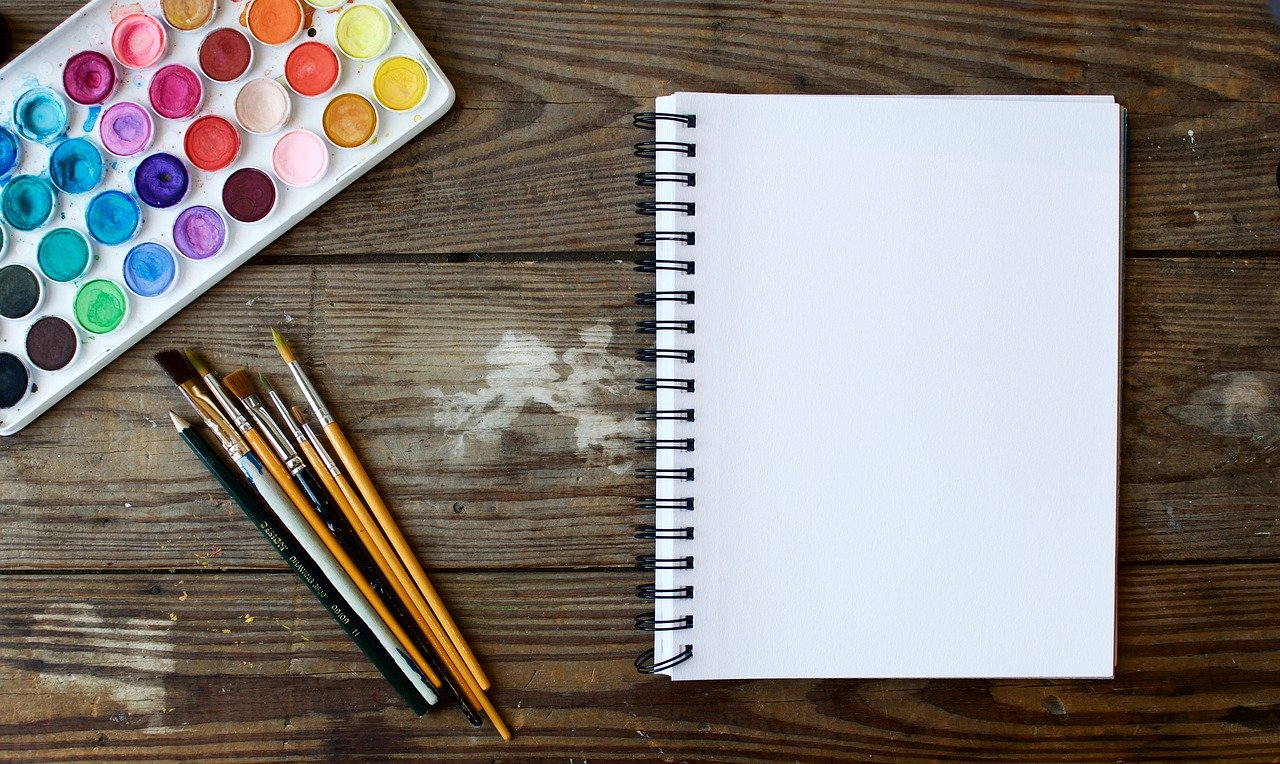
過去を振り返ると、「もう生きていくのが嫌だ」と思うような時期もありましたが、最後にはいつだって、「未来はよくなると信じること」で救われてきました。
人間が力を失うのは、どん底に落ちた時ではなく、明るい未来が見えなくなった時です。どん底に落ちても、未来が見えているなら人は強く生きていけます。
この先はもう少し悪いニュースが続くと思います。そしてある時元に戻ったように見える世界も、それはもう元通りの世界ではありません。
だけど、
それは必ずしも悪い意味ではありません。
破壊の跡には創造が訪れます。
出社という既成概念の崩壊→テレワーク→成果主義への移行→実力が評価されやすい社会
雇用側・被雇用側のリスク回避によるホテルや対面接客の人手削減・減少→ロボットの導入→ドラえもん、ウォーリー社会の到来
宅配ロボットやAIの活用。5Gの世界はもうすでに始まっています。
私は高校生の頃に、
ある小説を書きました。
しっかりとした本としてではなく、
授業の課題で書いた小説です。
主題は「数年後の未来」というものでした。
その世界は、学校が全てオンラインになり、食事は今のように料理を作って食べるというものではなく、サプリ一つで済ませらまれる、そんな世界です。もちろん車はなくなります。
私は学校が嫌いだったので、行く意味がわからないといつも思っていました。オンラインで勉強をすれば家にいても勉強できるのにと。
その当時は働いていなかったので書きませんでしたが、社会に出て働くようになって思ったことは、高校生の頃と同じように、「会社も行く意味がない」ということでした。
今、図らずともそんな世界が現実のものとなろうとしています。
「学校・仕事はオンラインで」だけを見ると、「引きこもり社会かよ」と思うかもしれませんが、もちろんそういう世界を望んでいるわけではなくて、望んでいるのは皆が幸せに生きられる社会です。
その世界では、働き手はロボットで、ベーシックインカム制度導入後の私たち人間は、いつでも会いたい人に会いに行ける社会です。
「生活のため」と、人を人と思わないような人の下で働かなくて済むようになり、腰痛に苦しみながら介護をしなくてもよくなります。
友だちがいなくても大丈夫です。C-3POみたいなおかしくも温かみのあるやつもいます。ペッパーは人の感情を理解しようと頑張っています。
検索エンジンがパーソナライズ化されていったように、動画がテレビを超えようとしているように、私たちはもう、嫌な仕事をしなくても、嫌いな人たちとも会わなくてもいいんじゃないかと私は思うのです。
行きたい場所に行く。
生きたい場所で生きる。
会いたい人だけに会う。
売れないバンドマンや売れない芸人ががずっと売れないままでも楽しく生きていける。
「DV被害者に直接10万円を渡そう」なんて悲しい議論が議題にならない世界。
引きこもりやニートがいつでもやり直せる世界。杖をついたおじいさんがファーストフードチェーンを築き上げるような世界。
それが、私が夢見る世界です。
「そんな世界来るわけない」と切り捨てることもできますが、「そんな世界が来るかも」とワクワクすることもできます。
そうだ、
今窓の外を見たら、すごく晴れていたんですよ。
最近は外に出ないから天気予報を気にしなくなって、朝カーテンを開けた時に天気がわかる毎日です。
ただ、
晴れているのに、人っ子一人歩いていないんです。
あなたは想像できましたか?
私はできませんでした。
朝起きるとたまに「本当に今は現実なのか?」と思うこともあります。
誰がこんな世界を想像できたでしょうか?
きっと誰も想像できなかったはずです。
これが、ワクワクする未来が来ると私が信じる根拠です。
今はただ、針が真逆に振れているだけです。