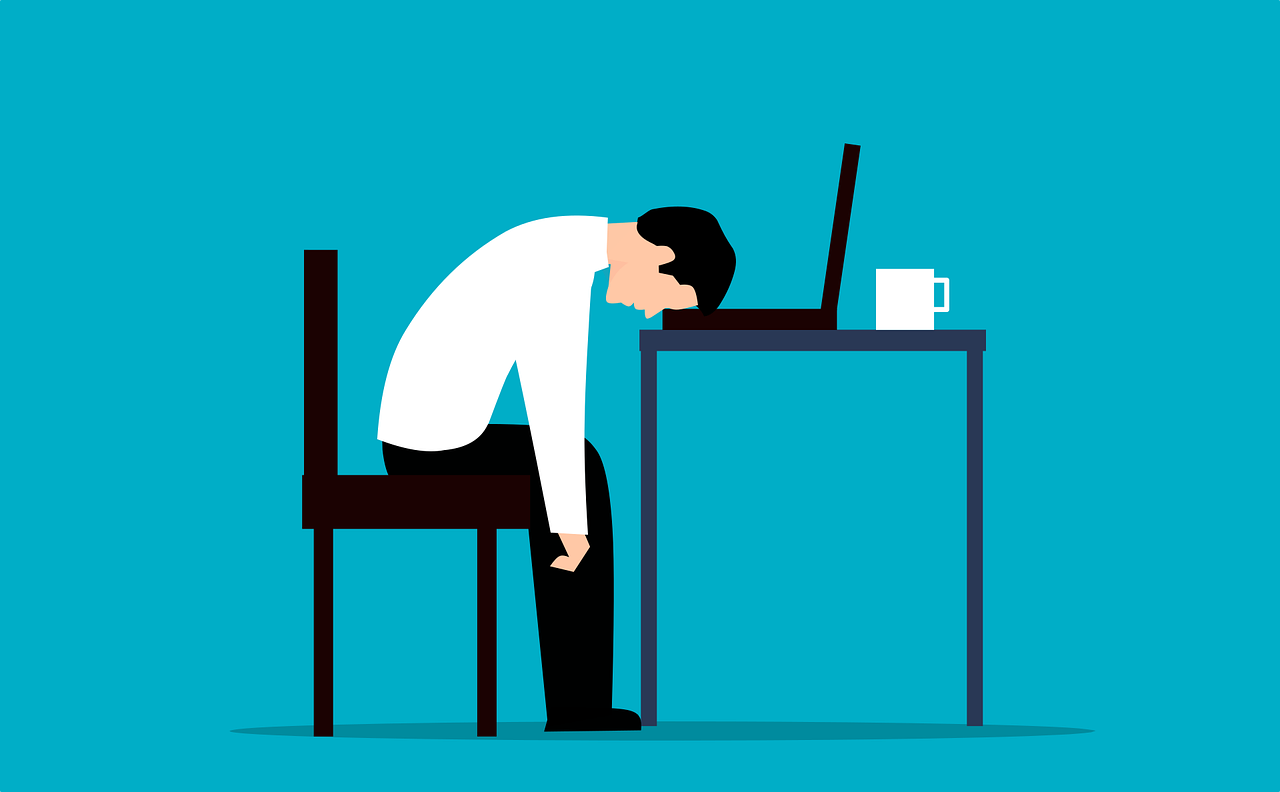「高いお金をかけてホームページを作ったのに、全然集客できない……」
「問い合わせも増えず、成果がまったく出ない……」
そんな悩みを抱えていませんか?
実は、集客できないホームページには“ある共通点”があります。
原因は、デザインや見た目ではなく、「設計の段階」で間違っていることがほとんどです。
この記事では、マーケティング視点で集客に失敗するホームページの特徴と、すぐに実践できる改善策をまとめました。
成果が出ないホームページにありがちな5つの原因

経営者の中には、大金を支払えば集客ができるホームページが作れると考えている人たちも多いですが、そんなことはありません。
500万円支払って1円も稼げないホームページも存在しますし、ワードプレスで自分で作って毎月何百万円もの売り上げをあげているホームページも存在します。
お金をかければかけるほど良いものが出来上がると思いがちですが、そんなことはないです。
この記事では、集客できない・効果がでないホームページになってしまう代表的な原因をまとめました。
マーケティング視点が欠けている

ホームページは「デザイン作品」ではなく、「集客のための営業ツール」です。
それにも関わらず、「何を誰に、どう伝えるか」というマーケティングの軸が曖昧なまま進行すると、見た目は良くても成果の出ないサイトができあがります。
たとえば、ホームページのメインビジュアル(一番目立つTOPページの画像の箇所)で訴求するべきなのは、見込み客にとってもっとも重要なことです。見込み客を惹きつける要素です。
ですが失敗するホームページのメインビジュアルのコピーでは、多くの場合、何も言っていないのと同じような当たり障りのない言葉が使われていたりします。
改善策①:ターゲットを明確にする(誰に何を届けるか)
よくある失敗パターン:
- ターゲットを広げすぎてしまい、訴求がぼやける
- ターゲットを“業界”や“年齢層”だけで定義してしまう
- 自社が届けたいメッセージを優先し、相手の悩みを無視している
ステップ1:理想の顧客像(ペルソナ)を1人に絞る
例)
「東京都内で美容院を経営している30代の女性。ホームページから予約を増やしたいが、SNSも使いこなせず困っている」
→ 名前や日常まで妄想することで、“刺さる表現”が生まれる
ステップ2:「悩みベース」でターゲットの関心を書き出す
- 集客に困っている
- 他社との違いをうまく伝えられない
- ホームページから何も成果が出ていない
ここを明確にすると、後述するコピーや導線がブレなくなる。
ステップ3:ターゲットが“今この瞬間に検索している言葉”を考える
→ 実際にGoogle検索で「ホームページ 集客できない」と入力し、サジェストや関連キーワードを調査
→ そこから「タイトル」「h2見出し」「本文キーワード」に反映
改善策②:メインビジュアルやキャッチコピーに顧客目線の訴求を入れる
よくある失敗パターン:
- 「信頼と実績の○○へようこそ」など、誰にも響かないフレーズ
- 抽象的なビジュアルで、何の会社かわからない
- キャッチコピーが自社の都合で書かれている
ステップ1:TOPに表示する“第一声”を「お客さんの悩み言語」で書く
Before:「〇〇株式会社は、未来を創るWebパートナーです」
After:「高いお金を払ったのに、ホームページから全く問い合わせが来ない…そんな悩みを解決します」
→ ポイント:「お客様の頭の中にある“心のセリフ”」を言語化する
ステップ2:キャッチコピーに「ベネフィット」を盛り込む
例:「SEOに強いホームページを、月3件の問い合わせに導いた実績多数」
→ 何が得られるのかを明示。実績や数字もあると信頼性UP
ステップ3:メインビジュアル画像の選定基準を変える
- 「きれい」「オシャレ」ではなく、「ターゲットが共感できる状況」を描いた画像を使用
例:ノートPCの前で悩んでいる社長のイラスト
→「これは私のことだ」と思ってもらえる
ステップ4:「ボタン(CTA)」も即行動できるコピーに変更
Before:「お問い合わせはこちら」
After:「今すぐ無料で相談してみる」
→行動意欲のハードルを下げる表現にする
2. デザイナーやディレクターのスキルが偏っている
見た目重視で「おしゃれ」に仕上げることを目的にすると、結果的に成果の出ないホームページになってしまうケースも少なくありません。
とくに、Webディレクターやデザイナーにマーケティングの知見がない場合、売れる構成になりづらいです。
ステップ1:制作会社の“選び方”を変える
多くの人が、制作会社を選ぶときに「実績の多さ」や「デザインの美しさ」だけで判断しがちです。
しかし重要なのは、「どんな成果を生んできたか」「どの業界で集客できたか」というマーケティング視点の実績です。
チェックポイント例:
- その会社が「業種ごとの集客導線」を理解しているか?
- 制作実績に「成果(CV率の改善・アクセス増加など)」の記載があるか?
- 担当者がマーケティングの知識を持っており、売上や集客の話が通じるか?
ステップ2:初回打ち合わせで“提案の質”を見極める
見た目やカラーの話ばかりする制作会社は要注意です。
初回のヒアリングで以下のような視点を持って話してくれるかどうかが、プロの分かれ目です。
良い提案をしてくれる会社の特徴:
- 「どんな人を集客したいですか?」と、ターゲット像から考え始める
- 「今のホームページで課題に感じていることはありますか?」と聞いてくれる
- デザインではなく、目的や戦略から逆算して話してくれる
ステップ3:制作の流れに“マーケティング担当”を入れる
ディレクターが制作の全体指揮をとるだけでは足りないケースもあります。
できれば、社内・外部問わず、マーケティング担当(コンサルタント)を制作チームに加えることで、視点のバランスが取れます。
- 外部にマーケティングだけ依頼するのもアリ(例:構成案やコピー監修のみ)
- 社内に「顧客目線」を持つ担当者がいれば、意見を反映する体制にする
ステップ4:「見た目」ではなく「動線と構成」に意識を向ける
ホームページの役割は、「かっこいい見た目を見せること」ではなく、訪問者を問い合わせや購入につなげることです。
- ファーストビューで「誰に向けたサービスか」が伝わっているか?
- サービス説明→実績→CTAという流れがスムーズに設計されているか?
- CTAボタンはページ内に複数配置されているか?
上記のように、「見た目」よりも「成果を出すための構成」が整っているかどうかを重視しましょう。
3. クライアント(依頼主)が口を出しすぎている

「この色が好きだから」「この写真のほうが社長のイメージに合う気がして」
「なんとなくこの文章だと弱い気がする」……。
気持ちは痛いほどわかります。
ですが、主観に基づいた細かすぎる修正指示は、ホームページを“自己満足の作品”に変えてしまいます。
とくに「顧客のためのサイト」ではなく「自分たちの好みを反映させる場」になってしまうと、集客やコンバージョンといった本来の目的からズレてしまうのです。
ステップ1:プロに任せるべき“領域”を明確にする
Web制作では、以下の項目は「ユーザー視点の最適化」が最優先されるべき領域です。
見た目や個人的な好みではなく、ユーザーの行動・心理に基づいて設計されています。
| プロに任せるべき項目 | 理由 |
|---|---|
| 色・配色 | 色彩心理や視認性に基づく設計がある |
| レイアウト | ユーザー導線を意識した配置がされている |
| フォント・余白 | 読みやすさ・信頼性に影響する |
| ボタンの位置や文言 | CV(問い合わせ・購入)への導線になる |
この部分を「自分の好み」で変更すると、成果が落ちる可能性が高いという意識を持つことが大切です。
ステップ2:クライアントが“伝えるべき領域”に集中する
プロが知らない情報、それがあなたの“武器”です。
依頼主であるあなたしか知らない 「現場の声」や「自社の強み」 にこそ、集客のヒントがあります。
たとえば、こういう情報は積極的に共有しましょう:
- お客様からよく聞かれる質問や不安
- 他社と比べられるポイント
- 社内で「これだけは他社に負けない」と思っている点
- 成約に至った時の決め手(実際のエピソード)
これらはすべて、キャッチコピーやUSP、コンテンツ内容に活かせる“顧客視点の宝”です。
ステップ3:「主観」と「目的」を切り分ける
「自分はこのデザインが好き」と思ったら、
一度立ち止まって、“誰のためのサイトなのか”を考えてみてください。
- あなたの“好き”は、ターゲットにとっても魅力的?
- その変更は、ユーザーの理解や行動を助けている?
- 変更の目的が「成果に近づくため」になっている?
この3点を問いかけてみるだけで、「なんとなく」ではなく戦略的な判断ができるようになります。
ステップ4:迷ったら“ABテスト”や“第三者の視点”で判断
どうしても迷うときは、「どちらが正しいか」ではなく「どちらが成果に近づくか」を軸に考えましょう。
- Google Optimizeやヒートマップツール(Clarity、Hotjarなど)で反応を見る
- 第三者(顧客候補やスタッフ)に意見を聞く
- LPであればABテストを実施する
「感覚」ではなく「データ」で判断すれば、納得感のある改善ができます。
4. USP(独自の強み)が打ち出せていない

ユーザーは「どこも同じようなことを言ってるな」と思いながら、複数のホームページを比較しています。
そんな中で、「なぜ他社ではなく、あなたの会社なのか?」が伝わらないと、すぐに離脱されてしまいます。
ですが、実際のホームページでは「創業〇年」「信頼と実績」など、他社と差がつかない“よくある表現”ばかりが並びがちです。
ステップ1:「USPとは何か?」を正しく理解する
USP(ユニーク・セリング・プロポジション)とは、
“お客様が、他社ではなくあなたの会社を選ぶ理由”です。
重要なのは、「会社の自慢」ではなく、お客様にとって価値があることです。
“社長が頑張ってる”ではなく、“顧客が得をする”内容でなければなりません。
ステップ2:「自社の選ばれる理由」を言語化するワークを実施する
次の3ステップで、自社のUSPを明確にしていきましょう。
(1)既存顧客に「なぜ選んだか」を聞く
- 「価格がわかりやすかった」
- 「説明が丁寧で安心感があった」
- 「問い合わせ後の対応が早かった」
主観ではなく“顧客の声”からヒントを得る
(2)競合サイトを5つ見る
- 何をアピールしているか?
- 自社と違う点はあるか?
- 差別化できそうな視点はあるか?
“違い”を探すのではなく、“違いを見せる言い方”を考える
(3)「それで、誰がどんな風に喜ぶのか?」で深掘りする
たとえば「24時間対応可能」なら…
✕:ただの便利なサービス
◯:「夜中に急なトラブルがあっても、安心して連絡できる」と顧客が感じられることがUSP
ステップ3:USPは「1ページ目」で伝える
せっかく考えたUSPも、見込み客が最初に目にする場所に書かれていなければ意味がありません。
表示位置の具体例:
- ファーストビューのキャッチコピー下に簡潔に
- 「私たちの強み」セクションをトップページ中段に設ける
- 事例紹介とセットで「〇〇が選ばれる3つの理由」などで展開
ただし、“業界用語だらけの抽象表現”はNG。小学生でもわかる表現で!
ステップ4:価格や実績よりも「顧客ベネフィット」を強調する
たとえばこう変換します:
| 書き方の例 | Before(会社目線) | After(顧客目線) |
|---|---|---|
| 価格訴求 | 「他社より安い」 | 「コストを抑えつつ、必要な機能が全部そろいます」 |
| 実績訴求 | 「累計500件制作」 | 「相談から公開までの流れがスムーズで安心」 |
| サービス訴求 | 「スマホ対応しています」 | 「スマホからでもサクサク予約できると好評」 |
5. 制作会社が「納品したら終わり」思考になっている
「とりあえず見た目は整ってるし、納品できたからOK」
そんなスタンスの制作会社に任せてしまうと、ホームページは“完成した瞬間から劣化が始まってしまいます。
Webサイトは、公開してからがスタートです。
ユーザーの反応を見て改善し、少しずつ成果につなげていく――
そうした「運用型」の発想がない会社だと、最初に立てた目的すら達成されないまま終わってしまいます。
ステップ1:「運用まで視野に入れている会社」を選ぶ
ホームページは“作る”だけでなく“育てる”もの。
初期制作だけでなく、運用フェーズにも関与してくれるパートナーかどうかが、制作会社選びのカギになります。
質問例(打ち合わせで確認):
- 「公開後の改善提案やアクセス分析のサポートはありますか?」
- 「Googleアナリティクスやヒートマップでユーザー行動を見てもらえますか?」
- 「どれくらいの頻度で更新を想定していますか?」
単なる「納品型」か、「運用伴走型」かは、この質問で見抜けます。
ステップ2:契約時に“保守・改善の体制”を明文化しておく
あとから「それは別料金です」と言われないために、契約書やプラン説明で以下の点を確認しておきましょう:
- 月に何回まで修正・更新対応してくれるか
- アクセス解析のレポートは出るのか(頻度や内容)
- 定期的な改善提案や運用会議の有無
- サーバー保守・CMSアップデート対応の範囲
ステップ3:社内でも「更新の目的と効果」を言語化する
制作会社に任せきりにするのではなく、社内でも“このページは何のためにあるか”を意識して運用していく姿勢が重要です。
社内で共有すべきこと:
- 各ページの役割(集客/商品理解/お問い合わせ導線)
- 公開後の目標数値(CV率、クリック率など)
- 次回更新時に改善したい点(滞在時間が短い、離脱が多いなど)
このように「目的 → 計測 →改善」というサイクルを意識することで、
“作って終わり”ではなく“成果を積み上げるホームページ”になります。
ステップ4:月1回の簡易チェックで“ホームページの健康診断”を
改善の第一歩は、「どこを直すべきかを見つけること」です。
専門知識がなくても、月1回5分で以下をチェックするだけで違いが出ます。
| チェック項目 | 見方・ツール |
|---|---|
| アクセス数の変化 | GA4(Google アナリティクス) |
| クリックされてるページは? | Search Console(検索パフォーマンス) |
| 離脱が多いページは? | GA4のエンゲージメントレポート |
| 問い合わせ導線が分かりやすいか? | 自分でスマホ操作して確認 |
「今月何が起きたか」を把握し、「どこを変えるべきか」を考える習慣をつけましょう。
まとめ:成果を生むホームページは“戦略”で決まる
高いお金をかけたからといって、必ずしもホームページが集客につながるわけではありません。
その違いを生むのは、見た目の美しさや流行のデザインではなく、「誰に、何を、どう伝えるか」という戦略的な設計にあります。
この記事でご紹介したように、集客できないホームページには共通する落とし穴があります。
- マーケティング視点が欠けている
- 制作者のスキルがデザイン寄りに偏っている
- クライアントの主観が前面に出すぎている
- USP(独自の強み)が伝わっていない
- 制作後の改善・運用が想定されていない
こうした課題を放置していては、どれだけ綺麗なサイトを作っても成果は出ません。
逆に言えば、これらを1つずつ丁寧に見直すことで、今あるホームページでも十分に生まれ変わる可能性があるのです。
ホームページは「完成」で終わりではなく、「育てていく」ものです。
ユーザーの視点に立ち、現場のリアルな声を活かしながら、地に足のついた改善を重ねていくことで、初めて「成果を出せる営業ツール」としての本領を発揮します。
一度立ち止まり、「本当に伝えるべきことは何か」「誰のためのサイトなのか」を再確認してみてください。
その気づきが、集客という成果につながる第一歩になるはずです。