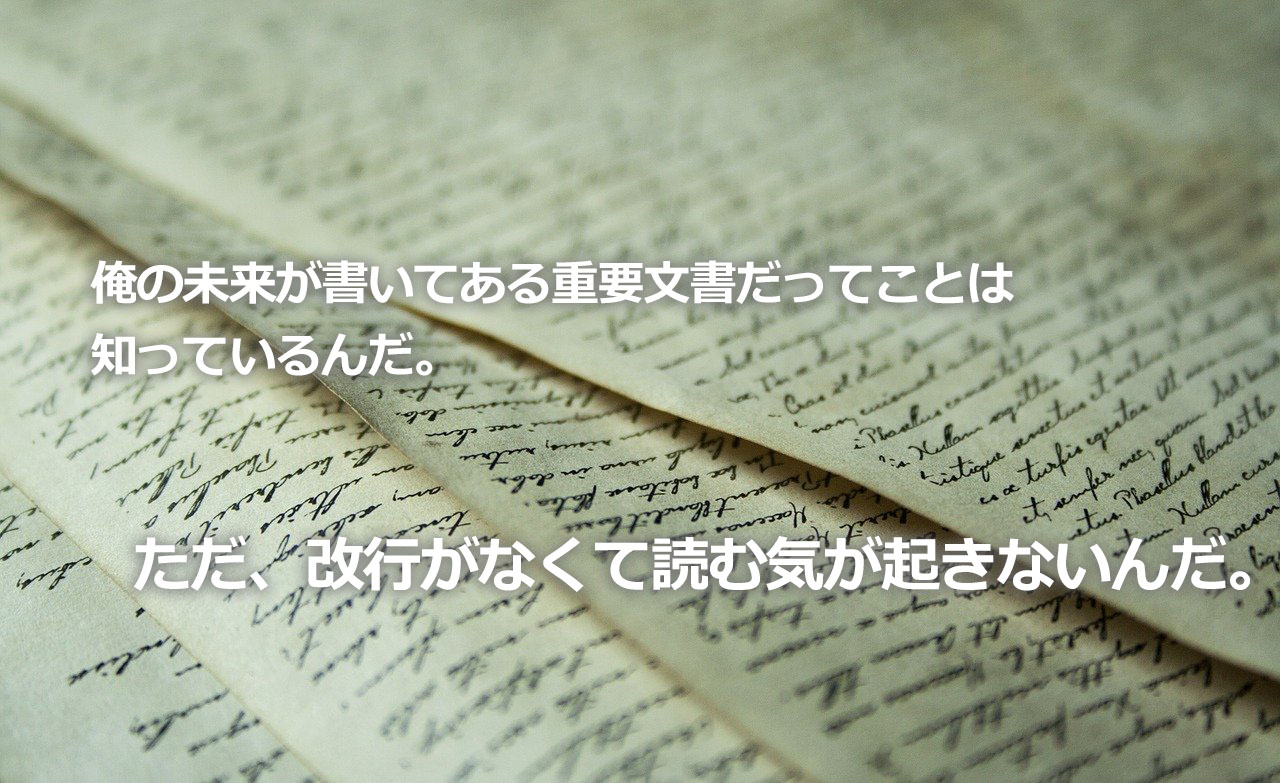あなたの書いたWeb上の文章、ちゃんと読まれていますか?
どんなに有益な情報でも、どんなにおもしろい文章でも、読まれなければ何の価値も生まれません。
読ませる前に読まれなければ話にならない
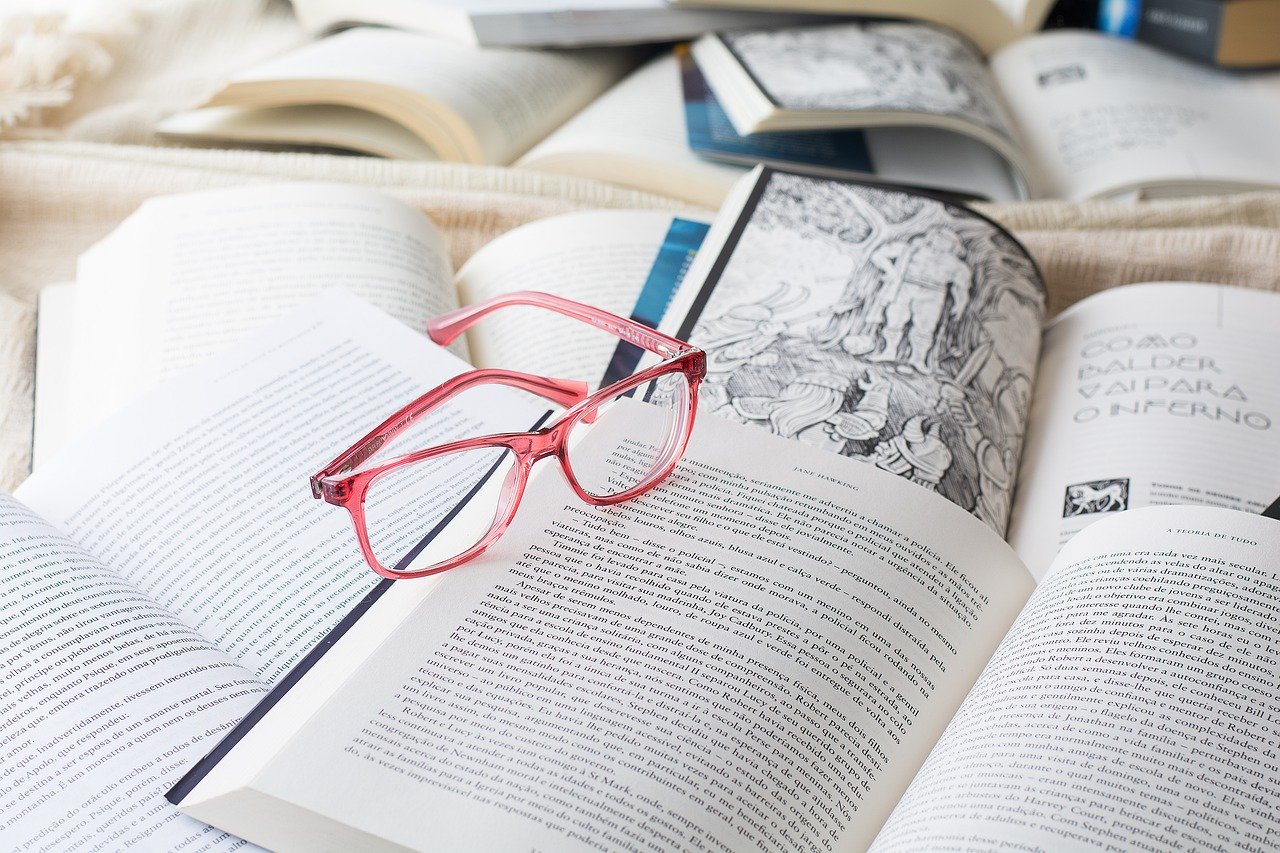
インターネット上の文章には、おもしろいかどうかはともかく、そもそもの話として、ユーザビリティが低すぎて読めない文章が多いです。
読めない文章というのは、もっと率直に言うと、「読む気にならない文章」のことでもあります。
インターネット上には数多くのテキストコンテンツがありますが、「読む気にならない文章」の割合は非常に高いです。そもそもの話ですが、「読む気にならないような文章」を書いている時点で、中身がどうかとかは関係ないです。
いくらコンテンツマーケティングのネタ探しに奔走しようが、伝える力がない場合には、Web上のコンテンツはゴミになります。
これは会話でのコミュニケーションを考えてみればわかります。
どんなに良い情報を持っていても、伝え方が適切でなければ、相手には伝わらないですよね?
Web上の文章の作法は、Webライティングやコピーライティング、セールスライティングなどと呼ばれたりしますが、これらは、会話でのコミュニケーションで言うところのメンタリズム、NLP、コールドリーディングのようなものです。
たとえばコミュニケーションのために、こういったテクニックを学べばより円滑に物事を進められたり、商品が売れたりするかもしれません。
ですが、かと言ってこういったテクニックを学ばなければ会話できないわけではないし、商品が売れないわけでもありません。
Web上の文書も同じで、Webライティングやコピーライティングといったテクニックを必ずしも学ぶ必要はありません。
ですが、上司や取引先との会話に正しい敬語が必要なことと同じように、一応最低限の作法くらいは知っておかないと、そもそも相手に読んでもらえないという事態が発生します。
たとえば企業の面接だって、面接のテクニックを学ばなくても合格できますが、最低限の敬語すらできなかったら、論外ですよね?
インターネット上には、この論外の部分すらできていない人たちがたくさんいます。
「読む気にならない文章」というのは、具体的に言うと下記のような文章です。
読まれない文章とは?
- 文字がびっしり詰まっていて読みづらい
- 見出しがないため、流し読みで意味が把握しづらい
- 難しい漢字を使いすぎている
- 一文の長さが適切でないため、意味が理解できない
それでは一つずつ見ていきましょう。
文字がびっしり詰まっていて読みづらい
たまにありませんか?
改行が一切なく、文字ばかりの文章。
あなたはそんな文章を見た時にどうしますか?
「うわっ」となって、最速で閉じませんか?閉じますよね。私だったらすぐに画面を閉じます。
それがどんなに良さそうな情報であってもです。
なぜなら、インターネット上には他にもサイトはたくさんあるからです。読みやすくて、同じような情報がたくさんあるからです。
なので、わざわざ嫌な思いをして文字がびっしりと詰まった文章を読む必要性はありません。
改行がなく、文字がびっしり詰まった文章というのは、人に心理的な圧迫感を与えます。
見出しがないため、流し読みで意味が把握しづらい
見出しのない文章も読みにくい文章になります。
見出しというのは、この記事でいうところの、他の文字と比べて少し文字サイズが大きくなっていたり、デザインが異なる部分です。
すぐ上の「見出しがないため、流し読みで意味が把握しづらい」のようなものを見出しと言います。
見出しの役割は、全体をパパっと見ただけで、内容をざっくり把握してもらうためにあります。
見出しで目を止めてもらえば、「もうちょっと詳しく知りたい」と思ってもらうことができ、詳細の中身を読んでもらえます。
難しい漢字や専門的な用語を使いすぎている。
漢字の多い文章も基本的に読みづらくなります。
漢字の多い文章は、心理的に「うわっ」と思われやすいですし、読めない漢字が出てきた場合には、いちいち調べなければならなかったり、読み飛ばしてしまったりするので、正確に意味が把握できない可能性もあります。
あなたがあまり英語が得意でないならわかると思うのですが、英語の文章を読むのってキツくないですか?
わからない単語が多くてイライラするし、わからない単語をその度に飛ばしていると、結局何の話かわからなくなります。
私は英語を勉強していて、その勉強のために洋書を読んでいるのですが、いつもイラついています(笑)。
一文の長さが適切でないため、意味が理解できない。
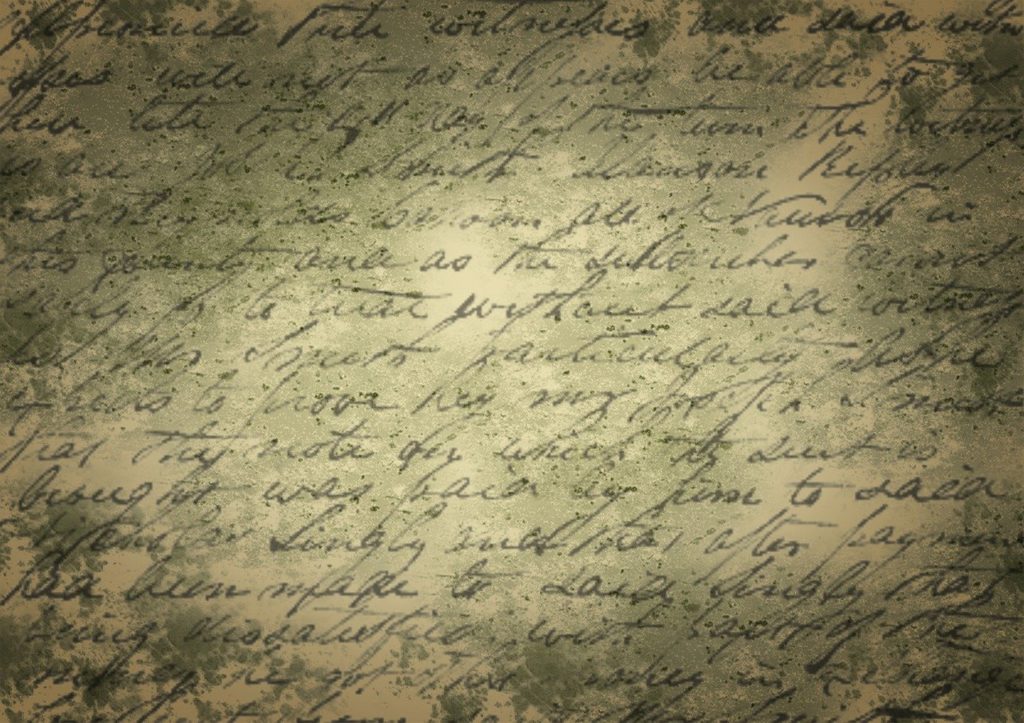
このへんは少し専門的な話になりますが、読まれるための文章を書くためには、一文の長さにも気を付けなければなりません。
なぜなら、一文が長すぎると意味が理解しづらくなるからです。
一つ例を挙げましょう。
【ダメな例】
私は冬休みに家族5人で福岡に行ったのですが、飛行機に乗って行き、福岡に着いてからはレンタカーを借りて観光をしました。福岡で食べたもつ鍋がすごくおいしかったのですが、福岡は海があるので、お寿司もとてもおいしかったです。
【良い例】
私は冬休みに家族5人で福岡に行きました。飛行機に乗って行き、福岡に着いてからはレンタカーを借りて観光をしました。福岡で食べたもつ鍋はすごくおいしかったです。また、福岡は海があるので、お寿司もとてもおいしかったです。
基本的には文を不必要に長くしていくと、意味が把握しづらい文章になっていきます。
接続詞を巧みに使って文章を長くしていくと、リンゴの皮を切らずに剥いていくような心地よさを感じなくもないですが、読み手にとっては読みづらい文章になります。気を付けましょう。
ただ、ここで気を付けなければならないことは、「じゃあ一文を短くすれば良いの?」といういことではないということです。
短い一文を淡々と書いていくと、アホみたいな文章になります。
私は冬休みに福岡に行きました。
家族5人で飛行機に乗って行きました。
福岡に着いてからはレンタカーを借りて観光をしました。
福岡で食べたもつ鍋はすごくおいしかったです。
福岡は海があるのでお寿司もとてもおいしかったです。
なんかアホっぽくないですか?
文末表現の影響もあるので、文の長さだけが原因ではありませんが、個人的には、みかんの皮をむく時に綺麗に根元に沿って向けずに、パズルのピースみたいにバラバラに剥いている人を見た時の感覚です。
わかりにくいですかね、すみません。
まずは読まれるために努力しよう

インターネット上で誰かに文章を読んでもらうためには、読んでもらうための工夫が必要になります。
読みやすいように余白を意識するとか、難しい漢字を使わないとか、言ってみれば、これらはすべて当たり前のことです。つまりは、「誰のために文章を書いているか」ということを意識する必要があるということです。
世の中には、自分たちの主張を声高に街中で叫んでいる人たちがいますが、なぜ彼らはほとんどの場合無視されているのかを考えてみれば、『そもそものWebライティング論』を考えることがなぜ大事なのかもわかります。
つまり彼らは、言いたいことを言っているだけなのです。
「誰のために文章を書いているのか」「誰に向けて文章を書いているのか」を意識すること。
これを忘れなければ、読まれる文章が書けます。
まとめ
インターネット上で誰かに文章を読んでもらいたいのなら、最低限の作法を意識する必要があります。
作法とは、言ってみれば読み手に対する敬意です。
「誰のために文章を書いているのか」「誰に向けて文章を書いているのか」を意識して文章を書けば、どんな文章を書くべきなのかがわかります。