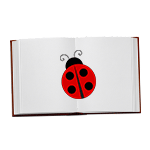社長・上司から指示されて必死に会社のブログを書いているけど思うような効果が出ていない。
始めにお伝えしておくと、企業ブログで成果を出すのは非常に難しいです。ブログを書いている企業は多いですが、そのほとんどが失敗しています。ブログを使ってうまく集客できているところはものすごく少ないです。今回はそのあたりの理由を書いていきます。
企業ブログが失敗する理由
なぜほとんどの企業ブログが失敗に終わってしまうのでしょうか?
考えられる理由は以下の通りです。
- 制約が多すぎて何の感情も動かせない記事になってしまうため
- Webライティングの知識・スキルがなさすぎるため
- SEOの知識・スキルがなさすぎるため
- 誰に向かって書いているのかを意識していないため
それでは一つずつ解説していきます。
制約が多すぎて何の感情も動かせない記事になってしまうため
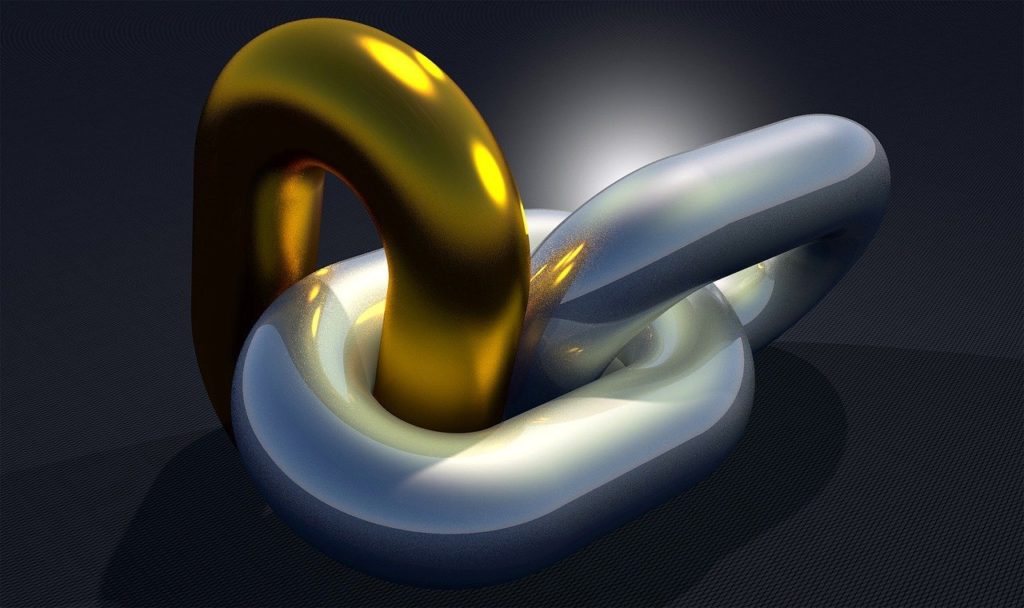
私もかつて、企業ブログの担当としてブログを書いていた時期があります。今だから言えますが、「誰にも読まれないだろうな」「クッソつまらない記事だな」と思いながら記事を書いていました。
その会社では、あらかじめブログのテンプレートのようなものがありました。こういう内容についてこういう文体で書く、というような決まりです。
新しい商品が出る度に商品名と説明だけ変えて、あとはすべて同じという更新方法です。
当然のことながら全く人が集まりませんでした。だってつまらないのですから、誰にも読まれるわけがありません。ライティングについて学び、形式を変えようとしたところ「そんな必要はない」と一蹴されました。
なので、結果として学んだライティングの知識・スキルは個人ブログに活かすことになったのですが・・・
閲覧者にとって役に立つ情報がない(売り込み、機械的な商品説明のみ)、おまけにつまらない、そんなブログを読みたいと思う人はいないはずです。
多くの会社ではブログを書く時に何らかの制約が存在するはずです。組織の情報発信手段である以上、下手なことは書けないですからね。
おまけに更新した記事は社内の人にも読まれる可能性があるわけで、それもあって当たり障りのない内容の記事しか書けなくなるわけです。
Webライティングの知識・スキルがなさすぎるため

これも大きな要因のひとつです。
仕方ないですけどね。おそらくほとんどのWeb担当者が、ちょっとパソコンが使えるからとか新人だからというだけでWeb担当になっているのですから。
この記事を読んでいるあなたは、きっとある程度Webリテラシーが高いのだと思います。なぜならこういう記事にたどり着くということは、Webの分野に少なからず興味があって、学ぼうとしているのですから。
もしもあなたが企業ブログを書いている、あるいはこれから書く予定があるのなら、Webライティングを学ぶのがオススメです。
SEOの知識・スキルがなさすぎるため
ライティングと並んで、ブログで成果を出すためにはSEOの知識も必要です。
SEO対策というのはSearch Engine Optimizationの略、日本語では「検索エンジン最適化」と呼ばれています。
SEO対策のプロと同じくらいの知識・スキルがWeb担当者に必要というわけではありませんが、ブログやホームページで結果を出すためには、多少のSEOスキルが必要になります。
たとえばあなたはこれらの質問に答えることができますか?
- 記事の文字数はどのくらいがベストなのか?
- タイトルの文字数は何文字が適切か?
- descriptionの役割は?
- 記事のh1とh2、h3などの役割は?
わたしがまだ会社で企業ブログを書いていた頃、これらの質問をされたら、一つも答えることはできませんでした。
SEO対策について詳しく知りたい場合は、SEO対策とは何かを解説した記事をお読みください。
誰に向かって書いているのかを意識していないため

誰に読んでほしいと思っているのかがハッキリしていないブログ、ものすごく多いです。
いや、もちろん表面上はわかっているはずです。
「誰に向かってブログを書いているのですか?」と聞いてみれば、「お客さんです」と彼らは答えます。ところがいざ記事を更新してみると、お客様が理解できるとは到底思えないようなブログ記事を書いてしまいます。
たとえば専門的で難しい言葉ばかり、漢字ばかりでそもそも読む気が起きないような記事。たとえば前提の説明を飛ばした数十文字くらいの記事。
往々にして、Web担当者はパソコンの画面の向こう側にいる人の存在を無視した記事を書きがちです。
ブログ記事を書く時は「誰に向かって」書くのかをきちんと意識する必要があります。
まとめ
- 制約が多すぎて何の感情も動かせない記事になってしまうため
- Webライティングの知識・スキルがなさすぎるため
- SEOの知識・スキルがなさすぎるため
- 誰に向かって書いているのかを意識していないため
組織に所属している以上、自由に書けない部分は仕方ないですが、自らが学ぶことで改善可能な部分もあります。