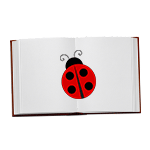- 将来が不安
- 先行きが不透明な世の中で強く生きていく方法を知りたい
先行きが見えない世の中で自分を見失わずに強く生き抜く方法

この記事では、先行きが不透明・見えない未来に対する不安や恐怖を和らげる思考方法を解説していきます。
全てを真に受ける必要はありませんので、ご自身の状況と照らし合わせながら読んでいただければと思います。
自分自身に「大丈夫」と言い聞かせよう

まず始めに勘違いしないでほしいのは、「大丈夫」という言葉の意味合いです。
たとえば飲酒運転で交通事故を起こした人は、「自分は大丈夫だ」と思っていたことでしょう。ですがもちろん、これは私が考える「大丈夫」とは異なります。
「自分は無敵だから大丈夫」ということでもないし、「自分は今までも大丈夫だったから大丈夫」といったものでもありません。
私が考える「大丈夫」とは、【何も起こらないから大丈夫】ではなく、【何かが起こっても大丈夫】といった意味合いです。
ですので少し補足すると、
「切り抜けられる(だから大丈夫)」とか「対応できる(だから大丈夫)」という意味になります。
この「大丈夫」という言葉が安心感につながっています。私は不安になる度に自分に「大丈夫だよ」という言葉を言っています。心の中でです。一日何十回と自分に呼びかけることもあります。
これはある意味、
【自己暗示】でもあります。
自己暗示とは、自分の意識にある概念を刷り込んで意識をコントロールする方法ですね。
ただ、ここでもまた勘違いしないでほしいのは、根拠もなく「大丈夫」と言い続けても信じるのは難しいということです。「大丈夫」という言葉を自分が理解するには、きちんとした筋道が必要になります。
たとえば近々仕事を失うかもしれない人が自分にかける「大丈夫」にはどんな根拠が必要なのかを考えてみましょう。
一番わかりやすいのは、「十分な貯金があるから大丈夫」という根拠です。
もっと筋道を詳細に立てるなら、
以下のようなイメージです。
- 仕事を退職した翌日に失業給付の申請する
- 仕事をしている間に引っ越して家賃を今よりも抑える
- 習い事を辞める
- 今勉強中の資格を取得する
- 取得した資格を活かして転職活動を始める
→「今の貯金で十分生活できる。だから大丈夫」といったことです。
筋道を詳細にすればするほど、
「大丈夫」という言葉は力を持ちます。
ある意味、「心配性、神経質」といった見方もできますが、私の場合、最悪の未来を想定して、その状況に対処する筋道を立てた時に安心感を持つことができます。
そしてその安心感を言葉で言い表すと「大丈夫」という言葉になるのです。
覚悟を決めるために「死」を見つめる
「何かあった時はそれはそれで仕方ない」というある意味達観した思考を持つためには、「死」の可能性を受け入れる必要があると考えています。
もちろん、私は一度も死んだことがないので、本当の意味で死を理解してはいないでしょう。そしてたとえば、もしも本当に死が目の前に見えたら、怖いと思ったり、泣いたりするでしょう。きっとそうです。
ですので、
「死ぬのなんて怖くない」と言ったら、それはウソになるでしょう。
ですが少なくとも、人生における「死の可能性」はごく一般的な人と比べたら理解しているつもりです。そしてその理解が、先の見えない恐怖を和らげてくれていることは確かです。
「死ぬのが怖くない」と言う人の中には、過去に死ぬ直前のような経験をした方が多いと思います。しかし私は、過去に死にそうになったことはありません。事故も病気も、何もないです。
近しい人やペットの死を経験したことはありますが、自分が死を感じたことは一度もありません。人生には、死生観が定義付けられる瞬間というのが、いくつかあると思います。私の場合にもいくつかあります。
たとえばその中の一例を挙げると、私の死生観を定義付けたのは、スティーブ・ジョブズの死と、小林麻央さんの死でした。
小林麻央さんの訃報が速報で流れた時、私の中で【幸福】に対する幻想みたいなものが壊れました。
美人で、お金持ちでイケメンな旦那さんがいて、可愛いお子さんがいる人は、生涯を幸せに終えると思っていました。
病の公表があった後も、「きっと大丈夫だろう」と思っていました。ところがそうではなかった・・・
この瞬間、私の中にあった【幻想】のようなものが壊れました。
余談ですが、私は小林麻央さんが生前残した『小林麻央オフィシャルブログ『KOKORO』」は、日本一のブログだと思っています。
どれだけライティングを勉強してもSEOを勉強しても、彼女のブログは越せない、というか次元が違います。
彼女の文章はすごく温かいというか、文字に心が宿っている気がします。彼女の文章を読んだり、笑顔の写真を見たりすると、生きていることにすごく感謝できるし、少し優しくなれる気がします。
たとえばまた別の例ではスティーブ・ジョブズです。スティーブ・ジョブズの生き様や残した言葉によって、私はすごくたくさんの影響を受けました。
人生を左右する分かれ道を選ぶとき、一番頼りになるのは、いつかは死ぬ身だと知っていることだと私は思います。ほとんどのことが—周囲の期待、プライド、ばつの悪い思いや失敗の恐怖など—そういうものがすべて、死に直面するとどこかに行ってしまい、本当に大事なことだけが残るからです。自分はいつか死ぬという意識があれば、なにかを失うと心配する落とし穴にはまらずにすむものです。人とは脆弱なものです。自分の心に従わない理由などありません。
『Steve Jobs』ウォルター・アイザックソン/井口耕二訳 288p 講談社
他にも、死の病におかされた人たちが残した言葉、「人間が死ぬ前に後悔する言葉」、武装地帯での生活の記録など、たくさんのことを学びました。
そうやって私は「死」を理解し、
人生に覚悟を決めてきました。
また、「死」に対する恐怖というのは、「あの時〇〇していればよかった」とか、「もっと〇〇したかった」とかといった、後悔と通ずる部分もあります。
- 死ぬ前に生きたかった場所
- 勇気を持って愛の告白をすればよかったこと
- 実家のおじいちゃんおばあちゃんにもっと会いに行けばよかったこと
- 両親に「ありがとう」と伝えておけばよかったこと
- 嫌な仕事をさっさと辞めればよかったこと
- まわりの目なんて気にしなければよかったこと
やり残していることが多ければ多いほど、平時の時にはそれが頑張るモチベーションになったりしますが、いざ危機が迫った時には、「まだ死にたくない」という恐怖につながってしまいます。
「まだ死にたくない」と思うことは全く悪いことではありませんが、恐怖がパニックにつながってしまったら、冷静に行動ができなくなります。その点、あまりまわりの目を気にせずに自分の思うままに生きていると、人生に後悔って少なくなります。
たとえば私は、会いたい人にはしょっちゅう会いに行きますし、パッと思い付きで旅行に行ったりします。今はないですが、翌日が仕事でも朝まで遊んでいたりしました。かと思えば、休日なんてとらずに誰よりも働くこともあれば、一年間ほとんど遊ばずに勉強することもあります。
無職で笑われようが気にならないし、褒められておだてに乗ることもありません。失敗して恥ずかしい思いをしても、帰り道でズボンのチャックが空いてることに気付いても平気です。まぁこれに関しては見てしまった方には申し訳ないですが。
それは全部、死んだら全てなくなることを知っているからです。死んだら全てなくなるのに、まわりの目に人生を決められるのなんて御免です。
もしもこれから先、「一つの会社の固定のメンバーと墓場に入るまで共に過ごさなければならない」と言われたら、そりゃもう少しまわりの顔色をうかがったりするでしょうが、まぁそんなことはないですよね。
あなたの上司も、部下も同僚も、失敗を笑う人たちも陰口を言う人たちも、パワハラをする人、会社の人たち皆、それにプライベートの友達だって、人生の最期には隣にはいてくれません。
たとえば人生の最期になって、上司に向かって「あなたのせいで仕事が嫌いでした」と言ってみても、「いや、そんなの知らんがな」と言われるのがオチです。そして実際にその通りです。
既卒ニートでも、公園で泣きながらお酒を飲んだ日々も、あっても大丈夫

もう少し具体的な話をさせていただくと、「なんとかなる」「大丈夫」といった自信は、臨死体験とまでいかずとも、人生のどこかの地点での経験が影響しているとも考えられます。
たとえば最近読んだ本で言えば、世界的なデザイナー佐藤オオキさんは、公園で生活するホームレスとお酒を飲む仲になったことがあり、その時の経験が「何かあっても大丈夫」という精神的なストッパーになっているそうです。
「この人なんか悟り開いてるんじゃ?」という雰囲気の人には、人生のどこかの地点でスティーブ・ジョブズの言うところの、「頭をハンマーで殴られるような経験」をしている人たちが多いです。
現アメリカ大統領のドナルド・トランプ氏だって、彼の出身は不動産デベロッパーの起業家ですが、過去には借金を背負ってどん底を経験したこともあるようです。
孫正義さんは病で長期間入院していたこともありますし、ホリエモンだって、時代の寵児から一瞬にして刑務所まで送られるような経験をしています。
ドナルド・トランプや孫正義の後に自分のことを書くなんておこがましいですが、私の場合、まわりの目を気にせずに生きるようになったキッカケの一つとして、既卒ニートを経験したことが大きいです。
既卒ニートになった経験は、それまでの人生の中で大した挫折を経験して来なった私にとってすごく大きな挫折になりました。
同年代のまわりの皆が「初任給で買うもの」の話をしている端で、私は「既卒 人生終わり」とスマホで検索していました。
「公務員になればいい」という言葉を信じて公務員を目指そうかなと考えたり、「大学院に行けばいい(卒業前)」という言葉を信じて色々な大学院を調べたり、もう本当先が見えない状態でした。
ニート期間を1年とちょっと過ごした後に最終的に会社員として働くことになったのですが、そこでの仕事もあまりうまくいかず、うつ病直前くらいノイローゼ状態になったこともあります。

また、辞めた後にインターネットで稼ごうと思ったものの失敗し、貯金が尽きかけ、夜の公園で「人生もう終わりだ」と缶チューハイを飲んだこともあります。

過去を振り返った時に決して誇れるものではないそんな経験の数々が、こと見えない未来を生きるとなった時に背中を支えてくれることに気付きます。必ずしも、「あんな経験をしたんだからどんなことがあっても大丈夫」とは思えません。
たとえば身近な人の死はそれぞれの死が悲しいのと同じように、ツライ体験はそれぞれ独特のツラさを持っています。「一個会社をつぶしたことがあるから、またつぶしてもいいや」とは思えないでしょう。むしろ、「もうあんな経験は絶対に嫌だ」と思うはずです。
ですが、過去のどん底の経験がどこかで恐怖を和らげているのは間違いありません。これは私の経験として言えます。
あなたにも「今だったら考えられないわ」ということを乗り超えた経験がありませんか?
足掻いてもダメな時は、頑張らなくてもいい。耐え忍んでチャンスを待つ

先が見えないと感じる時は、世の中の情勢が不安定だったり、あなた自身の状況が不安定だったりする時の場合が多いと思います。
何もかもがうまくいっている時であれば、「先が見えない」と不安になることもないですからね。
たとえば不安になるのは、
以下のような場合です。
- 仕事がなくなった
- 内定が決まっていたのに断られた
- 採用面接の不合格が続いている
- お金がない
すごく他人事かもしれませんが、私は人生には足掻いてもうまく波に乗れない時というのがあると思っています。そしてそういう時には、次のチャンスを待ってじっと耐え忍んでいたほうがいいんじゃないかとも思っています。
ドン・キホーテ創業者安田隆夫さんの著書にこんな過去の経験が書かれています。
その頃の私のライフスタイルは、徹夜麻雀をして朝帰りし、夕方にまたゴソゴソ起き出して雀荘に出かけていくという、自墜落を絵に描いたような毎日だった。
もっとも、当時のそんな体験が、のちにドンキの仕事で大いに役立つことになる。
うらぶれた気持ちで夜の繁華街をあてどなくさ迷いながら歩いた経験から、私には夜の街を漂流する若者たちの気持ちが痛いほど良くわかる。深夜市場の開拓や、ひとりで夜の街を徘徊する人々の心の襞に触れるドンキ流マーケティングが確立できたのは、当時の体験あってこそだ。
『安売り王一代 私の「ドン・キホーテ」人生』安田隆夫 30p 文春新書
慶応義塾大学を卒業し、ドン・キホーテというモンスター企業を作り上げた人でさえ、端から見たら「ダメ」と思われるような時期を過ごしています。
耐える期間も必要と考える。堕ちる時は再起できるレベルで落ちる

上に書いたように、人生には足掻いてもうまく軌道に乗れない時というのが往々にしてあります。
たとえば私は学生の頃、「自分は卒業したら銀行に勤めて、職場で出会った綺麗な女性と結婚して、幸せな家庭を築くんだ」と思っていました。
ところが、漠然と思い描いていた理想を実現する予定だった歳の時の私の現実は、無職、金なし、コネなし、コミュニケーション能力なし、のないもの尽くし。
おまけに、「ちょっと頑張ってみようかな」と思い立って受けた選考試験はことごとく不合格。
当座の生活費を稼ぐためにはじめた工場のアルバイトで、何も考えずに一日9時間商品を流す日々に、思い描いていた人生との違いを嫌というほど実感しました。
そしてそんな現実から目を背けるために、酒に溺れていったのです。
ですが、そんな状況の中でも気付きはありました。それは墜ちる時は意図的に堕ちた方が自分を守れるということです。
たとえば、酒に溺れてもいいけどアルコール依存症にはならないように気を付けるとか、ニート生活を送ってひたすら引きこもっていてもいいけど勉強するとかです。
私は、お酒をよく飲んでいた時期、同時にアルコールに関する資料やアルコール依存症の人の体験談などを読んで勉強していました。
そこでわかったことは、
アルコールはただの薬物であるというこです。
アルコールは「おいしいもの」「必需品」として世の中に広く浸透していますが、その本質は単なる薬物です。
ただ、薬物と言っても、所持しているだけで捕まるような薬物との決定的、かつ唯一の違いといっても差し支えないことが、「合法であること」です。この点が「危険」とされる他の薬物との大きな違いです。その点ではカフェインやニコチンも同じですね。
アルコールにしてもカフェインにしてもニコチンにしても、その本質を知っておけば付き合い方は変わるはずです。私の場合、アルコールの本質への理解が保険でした。
「保険をかけておく」ことができれば、極端な話、どんなどん底からでも必ず復活できます。
逆に言うと、再起できない人というのは、堕ちる時に保険をかけていないのではないかと私は考えています。
また、意図的に堕ちるというのはすごく大切なことだと思っていて、それは、生きる上で最も大切な「心」を守るためです。
コントロールできることに集中する。それ以外は捨てる

再び「未来」という抽象的な話題について触れていきたいと思います。
未来に限らず今を生きる上でも、多少のことでは動じない強さを持つためには、「自分がコントロールできることに集中し、それ以外は捨てる」という思考法も必要です。
この世の中には、自分の選択によってコントロールできることと、自分の選択ではどうしようもできないこととがあります。
たとえば、今からコンビニに行くという選択なら誰でもできるでしょうが、明日の天気予報を変えるということはできません。
テレビやネットのニュースに影響を受けやすい方や、まわりの目を異常に気にしてしまう方は、自分のコントロールできないことに意識を向けすぎているのではないかと思います。
世界情勢が悪い方に向かっているとか、政府の政策うんぬんとか、こういったものは全て個人のコントロールが効かない範囲になり、それは言ってみれば「どうしようもない」ということでもあります。
そして、「どうしようもないことは何とかしようとしたところでどうしようもない」ので、考えるだけ無駄だし疲れます。
これは別に、世界情勢を気にするなとか、政府の政策なんてどうでもいいと言っているわけではありません。たとえばビジネスマンにとって世界経済の流れを把握しておくことは大事なことですし、国民として政府の政策に目を光らせるのは大事なことです。
ですが、誰もがそれをやらなければならないわけではありません。少なくとも見えない未来に不安を感じてしまったり、恐怖を感じてしまう人、心穏やかに過ごしたいという人は、自分のコントロール下にないものにあまり意識を向け過ぎないほうが良いです。
人間にはキャパシティというものが存在します。世界情勢を憂いながら高校生の子どものお弁当を作る主婦はそう多くないでしょう。今日のランチを考えながら来年度の政府予算の配分に物申す女性はいないでしょう。
情勢とか環境といった大きな未来はコントロールできません。
今自分の目の前にあるコントロールできることに集中しましょう。
最高の未来と最悪の未来を想像する

「とは言ってもやっぱり未来のことが気になってしまう」という方も多いと思います。
世界情勢といった未来を正確に言い当てることは不可能ですが、予測することは可能です。そして予測に基づいて人生をシミュレーションすることも可能です。
たとえば、どこかの国がミサイルをいつ撃ち込んでくるかはわかりませんが、撃ち込んでくる可能性を想定することは可能です。先が見えずに不安という状態は、言葉通りになりますが、先が見えないから不安なわけです。
であれば、未来を予測してしまえば、ある意味先を見通すことにもつながります。
ですがかと言って、根拠のない占い師のように「きっとよくなるでしょう」といった予測では意味がありません。それは単なる現実逃避です。
未来予測をするうえで大切なことは、複数のパターンを持つことです。
未来予測というのは、
正確に言い当てるのは不可能です。
それはハーバード大学の教授であっても、大統領であっても同じです。
たとえば過去に破たんした伝説的な投資集団LTCM(ロングターム・キャピタルマネジメント)には、マイロン・ショールズ(ブラック=ショールズ・モデルの構築者)、ロバート・マートンという天才経済学者が在籍していました。
世界経済に多大な影響を与えたリーマンショックのことの発端は、米国の有名なリーマンブラザーズという証券会社でした。
天才が集まっても、
未来を正確に言い当てることはできません。
ではどうやって先を見通すかというと、上にも書きましたが、複数パターンの予測を持つことです。
わかりやすいのが、「うまくいった時のパターン」と「うまくいかなかった時のパターン」の2つの未来のシミュレーションです。
とくに、何かに挑戦する時というのは、この2つのシミュレーションに基づいてあらかじめ準備をしておくと、挑戦に対するハードルがすごく低くなります。
たとえば、会社を辞める場合のシミュレーションです。
【うまくいった時のパターン】
退職後は旅行したり、勉強したりして、少し自分の時間を持ちたいと思っている。
→一通りやり尽くした後に、勉強していた分野で転職→転職成功→給料アップ/素晴らしい仲間に恵まれる
【やること】
- 予算の配分
- スケジュール計画を立てる
- 入りたい分野の会社について調べる
【うまくいかなかった時のパターン】
退職後に旅行したり、勉強するまでは計画通りだが、「勉強が思った通りに進まない」「資格試験などに落ちる」などが発生。
【やること】
- うまくいかなかった時のパターン用の予算配分を考える
- 転職活動を早めに始める
- 自分のスキル・資格などを棚卸して働ける可能性の高い職種を探しておく
- 家賃など、固定費をあらかじめ減らしておく
- 副業収入を得ておく
うまくいった時のパターンに関しては、思い描いていた通りに進めば良いので何か特別な準備が必要なわけではありませんが、うまくいかなかった時のパターンの場合には、シミュレーションに応じて、様々な準備が必要です。
結果として2つのパターンがシミュレートできたわけですが、実際の行動は、楽観論・悲観論どちらに転んでもいいように行動します。
これは先に述べた「保険をかける」と同じような考え方ですが、保険をかければかけるほど見えない未来や挑戦に対する恐怖は減少していきます。
自分を棚卸して安心感を持つ

保険をかけるというところに関連して言えば、自分のスキルや資格、経験を棚卸することで、見えない未来に対する安心感を持つことができます。
たとえば、
以下のような棚卸しができます。
- 学歴
- 経験
- 貯金
- ルックス
- 家計
- 若さ
人にはそれぞれ強みになる部分、そして、かつ生きていくために活用が可能、または社会で必要とされるスキルや資格、経験などがあると思います。
たとえば何の資格も持っていなくても、「若さ」があればなんとかなります。若さはお金ではかえないスーパーチケットなので、市場価値はものすごく高いです。
たとえばルックスが良いというのも強みです。
「最悪全て失っても、YouTubeとかで顔出しで稼ぐか」といったことでも、安心感につながります。
不安な世の中で強く生き抜くための具体的な方法

さいごに具体的な行動の話をして終わりたいと思います。不安な世の中で生きていくために大切なことはいくつかありますが、その一例として私が日々意識していることは次のことです。
- テレビは見ない
- 人の話は聞かない
- 自分の頭で考える
- 信じる人を選ぶ
詳細を書きます。
テレビは見ない
テレビは見ません、
というか所有していません。
なぜかというと、
テレビには雑多な情報があまりにも多いからです。
たとえばニュース一つとっても、必ずしもそのニュースは真実をありにままに放送しているとは言えません。
視聴率を維持するためにキャッチーに加工されていたり、一方の側面だけに光を当てた報道がされたり、基本的にメディアという存在には、カメラ・編集を通す時点ですでにフィルターがかかっています。
たとえばバラエティー番組のやらせが発覚した時に驚く人はいますが、むしろ私は、やらせじゃない番組が存在するほうが驚きです。
また、テレビには不必要に不安を煽ったり(おそらく悪気はありません)、あるものを実態以上に良いものに見せようとする側面があります。
私がテレビを見ない一番の理由は「時間の無駄」だからですが、「情報」の面から見ても、テレビが生活に必要だとは思えません。
人の話は聞かない
世界情勢が不安定な時などは、
あまり人の話を聞かないほうがよいです。
「現実逃避しろ」ということではなくて、SNSやカフェでのおばさん同士の噂話なんてのはその最たる例ですが、正しく未来を見据えている人なんてほぼいないと思って間違いないです。
テレビの報道番組の芸能人だってそうです。それっぽいことを言っている芸能人はたくさんいますが、芸能人という後ろ盾をとってみてみれば、価値があるのかといえば微妙でしょう。
たとえばインターネットで「既卒 人生終わり」などと検索した時に(私は既卒になった時に実際に検索しました)、「一度既卒になったら人生終了」といったような情報が出てきますが、そもそもの話、「『一度既卒になった人生終了』と言っている人って誰なんですかね?」ということです。
もちろん特定の誰なのかという点もそうですが、「情報発信者として得をする可能性があるのは誰なのか?」という点も考える必要があります。
情報の裏を少し考えてみましょう。
- 実際に既卒になって人生が終わった人。「人生が終わる」の定義って何でしょう?
- 日常でストレスが溜まっている人がストレス解消に「既卒 終わり」とか「ニート 終わり」などと書き込んでいる。
- 就活サイトの関係者が不安感を煽るために書き込んでいる。
実際に既卒になった人が発信しているとしたら、それは個人差があるということですし、ある地点で終わっていると感じたのか、それとも死ぬ直前に終わっていたと実感したのか、あるいは、そもそも「終わる」の定義はどこにあるのか?が不明です。
ストレス解消に書き込まれた発言であるなら、根拠はないに等しいでしょう。
就活サイトの関係者が危機感を煽り、何らかの行動を意図して情報発信をしていると仮定するなら、この場合、発言は全てポジショントークになります。
少し仮定を出したところで改めて、「既卒 人生終わり」の情報発信者は誰なのかを考えてみましょう。
答えは、わからないです。
発信者のバックグラウンドが見えなければ信じるに値しない情報を真に受けるのはどうかと思います。
これはもっと身近な場所でも言えることです。
たとえばあなたは会社を辞めようと誰かに相談した時、「どこに行っても同じ」というようなことを言われたことがありませんか?
私はあります。
もっと汎用的な言葉にするなら、たとえばあなたは、何かに挑戦しようという時に、「どうせ無理だよ」と誰かに言われたことはありませんか?
「どうせ無理だよ」と発言したその人は、なぜあなたに「どうせ無理だ」と言ったのでしょう?
そこの明確な根拠はありましたか?
自分が無理だったらかとか、たぶん無理そうだったからとか、そんなあいまいなものではありませんか?
たとえば私は中学生の頃に、担任の先生に「志望校に受かる可能性はほぼない」と言わたのに関わらず、努力の結果合格した時、人生において他人の言葉を聞くのをやめました。
ただ勘違いしないでほしいのは、「じゃあ耳をふさいで生きればいいのね」ということではないということです。
自分の頭で考える
情報を収集する時に大切なことは、
自分の頭で考えることです。
- メディアが発信するニュースの焦点の当て方について考える。
- 友人の発言の意図を考える
- 芸能人やインフルエンサーの発言の意図を考える
- インターネットの情報の真偽を考える
- 投資家の発言がどの市場に影響を与えるのかを考える
ニュースで数字などのデータを見る時に気を付けなければならないことは、数値の切り取り方やグラフデータの作り方です。
グラフ類は加工が簡単なので、
とくに気を付けたほうがよいです。
自分の頭で考える習慣をつけることができれば、多数派よりも一歩先に行動することができますし、たとえばSNSなどの情報にまどわされることもなくなります。
信じる人を選ぶ
情報が溢れる時代で流されずに生きる方法の一つは、信じる人を選ぶということです。
上にも書きましたが、私はほとんどの人の話を真に受けません。こと人生を左右するような選択に必要な情報に関しては、日常で出会う人の99%の人の話は聞きません。ですが逆に、自分が「この人だ」と思った人に関しては、心から信じます。
不安定な世の中になるとどこからともなくリーダーが立ち上がってカルト集団化するといったら、小説のようですが、実際のところ、信じるものがある人は強いと思っています。
それは別に人でなくても構いません。
スティーブ・ジョブズの言葉を借りるなら、「何かを信じなさい」ということです。
まとめ
月並みが言葉で言えば、世界は今、グルグルグルグルと目にも止まらぬスピードで変化しています。「今」がいつを指すのかはここでは述べません。
なぜならおそらく、これから先もずっと世界はグルグル回転していくからです。もちろん過去だってそうでした。ですので、「今」が意味する時とは、この記事を読んでくれているあなたが生きている時代のことになります。
この記事自体も、長く汎用的に通用するような内容になっています。
この記事では、「先が見えない未来を強く生き抜くための方法」を書いてきました。誰にとっても有効的かはわりませんが、少しでも参考になったらうれしいです。
明日は見えません。
でも生きていくことはできます。
きっといろいろなことはよくなると信じて、生きていきましょう。
それでは、お読みいただきありがとうございました。