「SEO対策に強いコーディングってあるの?」
「コーダーやWebデザイナーとして、検索に強いサイトを作りたい」
そんなあなたに向けて、現役でSEO業務に携わるマーケターである私が、コーディング時に意識している5つのポイントを解説します。
コンテンツの質が大前提とはいえ、検索エンジンが正しく評価できる構造を作ることも大切。
ほんの少しの工夫で、検索結果に差が出ることもあるので、ぜひ実務に活かしてみてください。
SEO対策に有効なコーディング

本格的なSEO対策を考えた場合、「どのようなコーディングをするか」というテーマは避けて通れません。
SEO対策の施策のなかで、「コーディングの良し悪し」が占める割合はそこまで高くありませんが、せっかく良いコンテンツを作っても、コーディングの質のせいで評価されなかったらもったいないです。
ですからコーディングの質には注意する必要があります。
この記事では、普段私が仕事のなかでチェックしているコーディングチェックポイントをご紹介します。
あなたがWebデザイナーやコーダーであれば、SEOにこだわりのあるクライアントからの依頼があったときに役立ちます。
あなたが外部にコーディングを依頼するサイト管理者であれば、成果物のチェックポイントとして利用できます。
【5つのポイント】
- エラーのないコーディングを心がける
- タグの意味を考えてマークアップする
- コードの記述順を意識してコーディングする
- ページ表示速度を落とさないためのコーディング配慮
- 見出しタグ(hタグ)の構造はSEOの土台
1.エラーのないコーディングを心がける

最低限のチェックポイントは、
エラーのないコーディングです。
少しエラーがあるからといって評価が下がることはありませんが、HTMLソースにエラーがあると、クローラーがうまくページを読み取れない可能性もあります。
具体的には:
- 閉じタグの忘れ
- タグの入れ子構造の崩れ
- 存在しない属性の記述
こうした基本的な文法エラーを防ぐことで、SEOへのマイナス要素を排除できます。
「W3C Markup validation Service」のようなチェックツールを使って、エラーのないコーディングを目指しましょう。
2. セマンティックなHTMLを意識したマークアップタグの意味を考えてマークアップする
「セマンティックWeb」と呼ばれる、「タグの意味を考えてマークアップをしよう」という考え方があります。
Webサイトに○○株式会社の記載があったとき、人間はそれが会社名だとすぐに判断できます。しかしロボットは判断できません。
ですから「意味のあるマークアップをしてロボットにもわかるようにしょう」というのが、セマンティックWebの考え方です。
意味のあるタグの例
- <header> <footer> → ページ全体の枠組みを伝える
- <nav> → ナビゲーションの明示
- <article> <section> → コンテンツブロックの区切り
- <h1>~<h6> → 見出しの階層構造を形成
一方、<div> や <span> は汎用的な装飾に使われますが、意味を持たないタグです。
可能な範囲で、意味のあるタグ=セマンティックタグを活用して検索エンジンに伝わる構造を意識しましょう。
3. コードの記述順は“上から評価される”ことを意識
コードの記述順を意識してマークアップしている方はあまりいないかもしれませんが、意外に大事です。
なぜコードの記述順が大事かというと、検索エンジのロボットがHTMLソースの上から順番に読んでいくからです。ですので、「上の方に重要なコードを配置する」というのが推奨です。
明確な根拠はありませんが、できるだけ早い段階で<body>内の目標キーワードを配置するというノウハウもあります。
また、コードの記述は、次に解説するページスピードにも関係しています。
具体的にコードの記述順をどう意識すれば良いかというと、主には<head>内の話です。
<head>内の上部にごちゃごちゃと<script>タグが入っているサイトがたまにありますが、最低限必要な<meta>情報を記述したら、早めに<title>を記述するのが推奨です。
<script>タグ類は<head>の閉じ直前あたりに記述しましょう。
4. ページ表示速度を落とさないためのコーディング配慮
SEOでは「ページスピード」が重要な評価指標です。コーディング時に以下を意識しましょう。
ページスピードを下げる原因:
- 非圧縮の大きな画像ファイル
- JavaScriptやCSSの読み込みタイミング
- 外部ファイルの読み込みが多すぎる
対策例:
- 画像はWebP形式や圧縮ツールを使用
- <script defer> や <link rel=”preload”> の活用
- CSSとJSの遅延読み込み(Lazy Load)でレンダリングブロックを回避
参考ツール:Google PageSpeed Insights
5. 見出しタグ(hタグ)の構造はSEOの土台
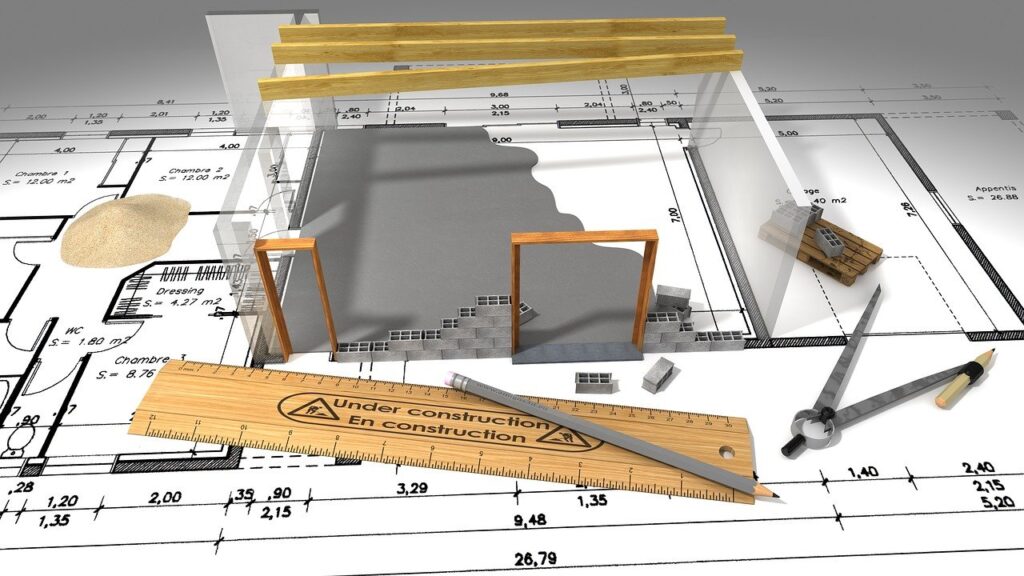
検索エンジンは見出しタグを読み、コンテンツの構成と重要度を理解します。
適切なhタグ構成例:
<h1>ページ全体の主題</h1>
<h2>大見出し1</h2>
<h3>小見出し1-1</h3>
<h3>小見出し1-2</h3>
<h2>大見出し2</h2><h1>~<h6>を飛び飛びに使っていても表示はされますが、構造が乱れるとSEO評価が下がる原因になります。
見出しタグは「文章構造の地図」。
きちんと階層を作りましょう。

まとめ|SEOに強いコーディングは「読みやすさ」の積み重ね
検索エンジンは、人間ではなくロボットが読み取る世界。
だから、ロボットが理解しやすいようなコーディングを心がけていきましょう。
- HTMLエラーをなくす(W3C準拠)
- セマンティックなタグで意味を伝える
- コードの記述順に配慮する
- ページ速度を落とさない設計にする
- hタグの構造を整える
どれも特別なスキルは必要ありません。
ちょっとした配慮で、Googleに伝わるコードが書けるようになります。
SEOに強いサイトを作るための“下地”として、ぜひこの5つをチェックしてみてくださいね。


