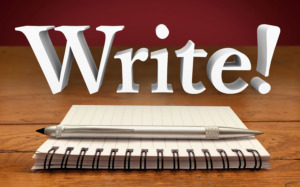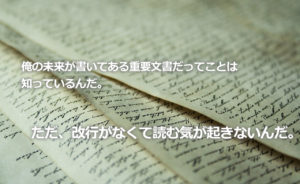メールやチャットでのやり取りで、
「何が言いたいのかよくわからない」
「ちょっと読みづらいかも」と言われた経験はありませんか?
文章でのコミュニケーションが当たり前になった今、読みづらい文章は誤解やトラブルのもとになりかねません。
本記事では、ブログ歴5年以上・1級Webライティング能力検定所持の筆者が、読みづらいと言われてしまう文章の特徴とその原因について、具体例を交えて解説します。
読みづらい文章の特徴
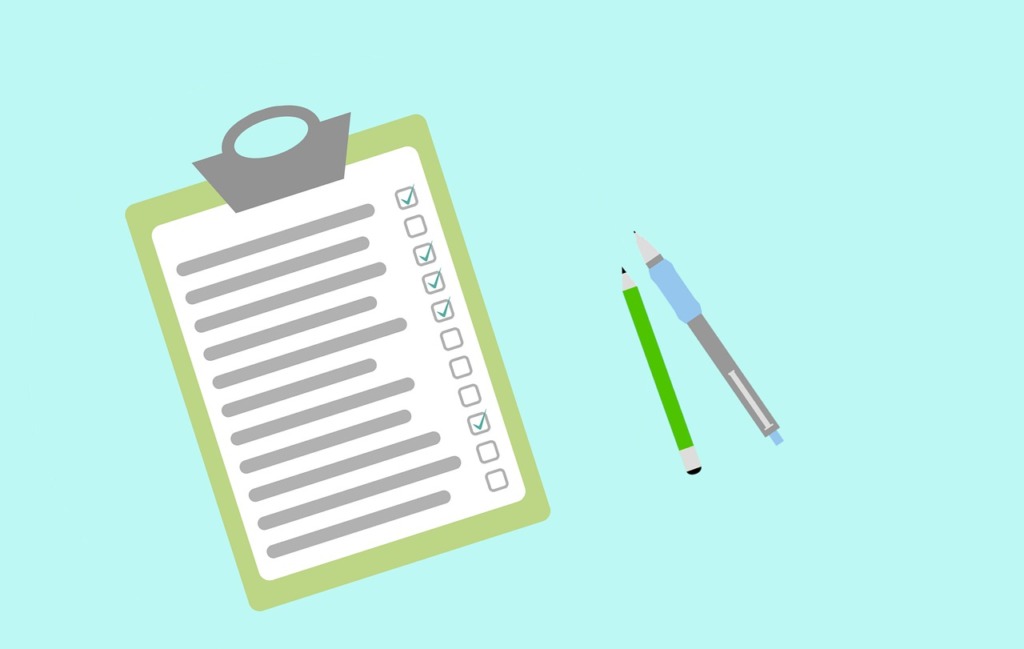
ビジネスの現場では、メールやチャットなど、文章だけで意思疎通を図る場面が少なくありません。だからこそ、「読みづらい文章」は想像以上に大きなリスクになります。
伝えたいことが正しく伝わらなければ、仕事の進行に支障が出たり、場合によっては誤解やトラブルにつながることも。
この記事では、そうした事態を防ぐために知っておきたい「読みづらい文章の特徴」をピックアップして解説していきます。
①結論が最後に書かれている
結論が最後に書かれている文章は読みづらいです。
なぜなら、最後まで読まないと書き手の主張がわからないからです。
最後まで書き手の主張がわからないと、結論にいくまでの文章をどのスタンスで読めばよいかがわかりません。
たとえば、「A案に賛成か反対か」といったテーマがあったとしましょう。
結論先行型の文章の場合、次のように書かれます。
私はA案に賛成です。なぜならA案は非常に素晴らしいからです。
結論先行型の文章の場合、読み手は、「この人はA案に賛成なんだ。じゃあこの後に続く文章はすべて賛成派というスタンスで読めばよいのか」とわかります。
では結論が最後に書かれている場合にはどうなるか。
A案は非常に素晴らしいです。私はA案を聞いてとても良い考えだと思いました。けれども、私はA案に反対です。
結論が後に書かれる場合、意外性を狙ったドラマの展開のように、最後の最後で立場が真逆に入れ替わる書き方も可能です。
そしてこういう書き方をしてしまうと、読み手は「賛成派だと思って読んでたのに、反対派だったんかーい」とツッコミを入れたくなります。
小説やドラマであれば起承転結の展開もありですが、ビジネス文章の場合には、避けたほうが良いです。
②接続詞の使い方を間違っている
接続詞を正しく使えていないと、
文章が読みづらくなります。
接続詞は、文と文との整合性をとるために必要なものです。
たとえば、「しかし」には、反論(逆説)の意味があります。
「また」には、並列の意味があります。
接続詞にはそれぞれ正しい使い方があるのですが、読みづらい文章を書く人は、使い方を間違っているケースがあります。
また、接続詞には、接続詞の後に続く文章のスタンスを事前に読み手に伝えるという意味もあります。
たとえば、「しかし」や「けれども」といった接続詞が出てきたら、読み手は、「この文章は反論(逆接)なんだ」と理解します。
「あるいは」という接続詞が出てきたら、「選択肢が複数ある文章なんだ」と気づきます。
このように、接続詞には事前に文章の意味を伝えるという大事な役割があります。
正しく使えるようにしておきましょう。
③指示代名詞の選択肢が多い
「あれ」や「こちら」といった指示代名詞を使うと、読みづらい文章になります。
なぜなら、文章のなかに指示代名詞があると、読み手はその指示代名詞が何を指すかを、頭を使って考えなければならないからです。
また、ひとつの文章のなかに指示代名詞の選択肢が複数あると、読み手は混乱します。
たとえば次のような文章があったとしましょう。
昨日テレビで観た『クレヨンしんちゃん』がとてもおもしろかったです。あれはやはり、大人になってから観ても良いですね。
おそらく「あれ」が指すのは『クレヨンしんちゃん』だと思いますが、「テレビ」という選択肢もあります。
「『あれ』が意味するのって『クレヨンしんちゃん』』であってますか?」と聞ける関係であれば問題ありませんが、ビジネスの場では、いちいち確認するのは難しいです。
その結果、勘違いしたまま話が進んだり、相手の貴重な時間を奪ったりすることにつながります。
④読点の使い方がおかしい
読点とは、「、」のことです。
読点の使い方がおかしい文章も読みづらくなります。
読点には明確な答えはないので、何が正しくて何が間違っていると言えない面もありますが、読点の位置によって意味が変わるような文章もあるので、使い方には注意が必要です。
読点は、「一時停止」のような意味をもっているので、一文のなかであまりにも使いすぎると、障害物が置かれすぎてて少しずつしか進めない障害物競走のように、イライラします。
逆に、読点をまったく使わないと、文章の意味が正しく伝わらなかったり、一瞬で去っていく流れ星のようにパッと読んでしまって、「あれ、今の文章なに書いてあっけ?」みたいなかんじになります。
⑤一文が長すぎる
一文があまりにも長い文章は読みづらくなります。
一文があまりにも長いと、文章の意味を把握しながら読むのが大変だからです。
たとえば、文章は「ですが」や「、(読点)」を使うとひたすら長くすることができます。
今日は天気が良かったので外に出かけたのですが、夕方から雨が降り出して、折りたたみ傘を持ってきたかどうかバッグの中を探したのですが、天気予報が晴れだったので結局傘は持ってきていませんでした。
状況としてはわかりますが、
読んでいて息切れしそうですよね。
読みづらい文章を書いてしまう人ほど、「つなげたほうが丁寧だ」と思って、文をどんどん長くしがちです。
ですが実際には、長い一文は負荷が高く、読み手の理解を妨げます。
もちろん、すべての文を短くすればいいというわけではありません。短すぎると、かえって散文的でリズムの悪い文章になります。
理想は、短めの文を基本にしつつ、ときどき長めの文をバランスよく混ぜること。
目安としては、一文あたり40〜60文字前後が読みやすいと言われています。
「長くなりすぎていないか?」と意識するだけでも、文章の印象はぐっと変わります。
⑥漢字やひらがなのバランスが悪い
漢字とひらがなのバランスが悪い文章も読みづらくなります。
漢字が多すぎると、見た目が黒くなって読み手に抵抗感が生まれますし、読めない漢字が出てくると、ストレスになります。
また、漢字と漢字を連続させると、読み手がふたつの漢字をつなげて読んでしまって、意味が正しく伝わらない可能性があります。
かといって、ひらがなばかりを使いすぎると、低年齢向けの文章だと思われますし、読みやすいと思いきや、文字と文字がくっついて見えて、読み進めるのが意外に大変です。
スマートフォンやパソコンで文章を書く場合、機械が漢字変換してくれるので、手書きでは書けないような難しい漢字を使ってしまう可能性があります。
漢字をたくさん使うと頭が良さそうに思えますが、読み手は読めなくてストレスになっています。
ではどうするかですが、迷ったら「ひらがな」にしておくのが良いです。
ライティング用語で、漢字をひらがなにすることを「ひらく」と言うのですが、私の場合、一般的な人よりもかなりひらいています。
あまりひらきすぎるとかえって読みづらくなる可能性もありますが、それでもひらいているのは、文章を読むのが苦手な人にも読んでほしいと考えているからです。
漢字を多用して文章を書いている人を見ると、「自分のレベルについてこれる人だけが読めばいい」というような感じがして、私は嫌です。
だから難しい漢字は使わないし、いちいち意味を調べなくても読み進められるような言葉を使うようにしています。
読みづらい文章の特徴まとめ
読みづらい文章については以上です。
読みづらい文章を書いてしまうと、意味が誤解して伝わってしまったり、「何が言いたいんだろう?」と考えさせてしまって、相手の時間を奪ってしまったりします。
逆に、読みやすい・伝わりやすい文章が書けると、コミュニケーションが円滑に進んだり、取引がスムーズに進んだりします。
ですから、意識して文章スキルを学ぶのがオススメです。