「SEOで大事って聞く“E-A-T”って何?」
「最近“E-E-A-T”って言葉も見かけるけど、違いはあるの?」
この記事では、現役SEOマーケターが「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の最新定義と、SEOにおける重要性、対策方法までをわかりやすく解説します。
E-E-A-Tとは?Googleが重視する4つの評価基準

E-E-A-Tは、Googleの検索品質評価ガイドラインに記載されている高品質なコンテンツを評価するための4つの指標です。
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trustworthiness(信頼性)
| 項目 | 日本語訳 | 意味 |
|---|---|---|
| Experience | 経験 | 実体験に基づいた情報か? |
| Expertise | 専門性 | 専門的な知識に基づいているか? |
| Authoritativeness | 権威性 | 第三者から評価・引用されているか? |
| Trustworthiness | 信頼性 | サイト全体として安心できるか? |
2022年末頃から「E-A-T」に「Experience(経験)」が加わり、E-E-A-Tとして進化しました。
なぜE-E-A-TがSEOで重要なのか?
Googleは「検索ユーザーに有益な情報」を届けることを最優先しています。
そのため、単なる情報の寄せ集めやAI生成の内容ではなく、人の実体験や専門知識に基づいた“本当に価値のある情報”を評価するようになっています。
とくにYMYL(Your Money Your Life)と呼ばれる、お金・医療・法律・健康・安全に関わるジャンルでは、E-E-A-Tの重要性が非常に高くなります。
E-E-A-Tの4要素をわかりやすく解説
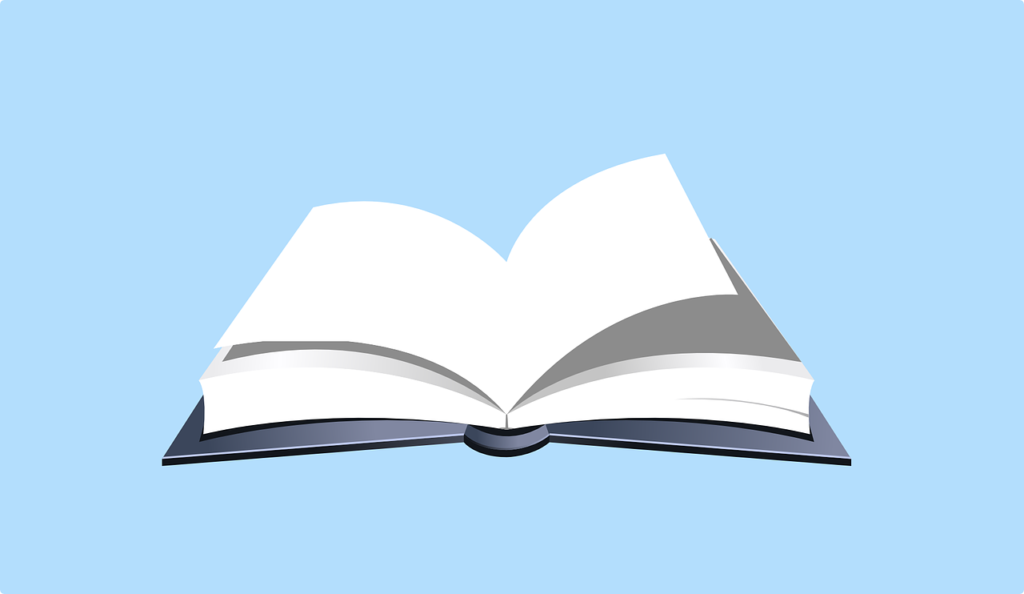
E-E-A-Tのそれぞれの単語について少し深堀りしてみましょう。
1. Experience(経験)
経験とは、「実際にその行動をしたことがあるか?」という指標です。
- 商品レビュー → 実際に購入・使用した経験があるか?
- 転職体験談 → 自分で転職活動をしたことがあるか?
-留学記事 → 実際に海外生活を送った経験があるか?
読者は「体験者のリアルな声」を求めているため、一次情報が含まれるほどSEO上の評価も高くなります。
2.Expertise(専門性)
専門性とは、その分野についての深い知識やスキルを持っているかどうか。
- 弁護士が書いた法律解説
- 管理栄養士による食事指導
- SEO担当者による検索アルゴリズム解説
など、資格・肩書き・職歴・実績の明記があると、より専門性が強く伝わります。
3.Authoritativeness(権威性)
権威性とは、「他人に認められているか」という観点です。
- 被リンク(外部サイトからの紹介)
- 引用・言及(SNSやブログで取り上げられる)
- 他の専門家との関係性(共同執筆や監修)
簡単に言えば、“その人がその分野でどれだけ信頼されているか”が評価されます。
4.Trustworthiness(信頼性)
信頼性は、サイト全体の設計や管理に関わる項目です。
信頼性を高めるために必要なもの:
- プライバシーポリシーの設置
- お問い合わせフォームの設置
- 著者情報・運営会社の明記
- HTTPS(SSL化)
- 正確な情報源の引用(厚労省、Google公式など)
匿名・無根拠・連絡先なしのサイトは、いくら内容が良くても信頼性が低く評価されます。
E-E-A-Tを高めるためのSEO対策

では、E-E-A-Tを高めるためには、
具体的に何をすれば良いのでしょうか。
1. 実体験を盛り込む(Experience対策)
- 商品レビューには自分の写真を入れる
- 体験談には時期・場所・感情を具体的に書く
- ChatGPTなどで生成しただけの記事に、自分のエピソードを足す
2. 著者の専門性を示す(Expertise対策)
- 著者プロフィールに職歴・資格を明記する
- 「運営者紹介」ページを作る
- SNSや他サイトの活動実績もリンクする
3. 権威性を高める工夫(Authoritativeness対策)
- 他サイトからの自然リンクを増やす(良質な記事を書く)
- 名前で検索されるような活動をする
- メディア露出、書籍出版、SNSフォロワーも評価される要素に
4. サイトの信頼性を整える(Trustworthiness対策)
- プライバシーポリシー・特商法ページを明記
- 記事に引用元(信頼できる一次情報)を記載
- SSL(https化)+スマホ対応
YMYLジャンルではE-E-A-Tが命
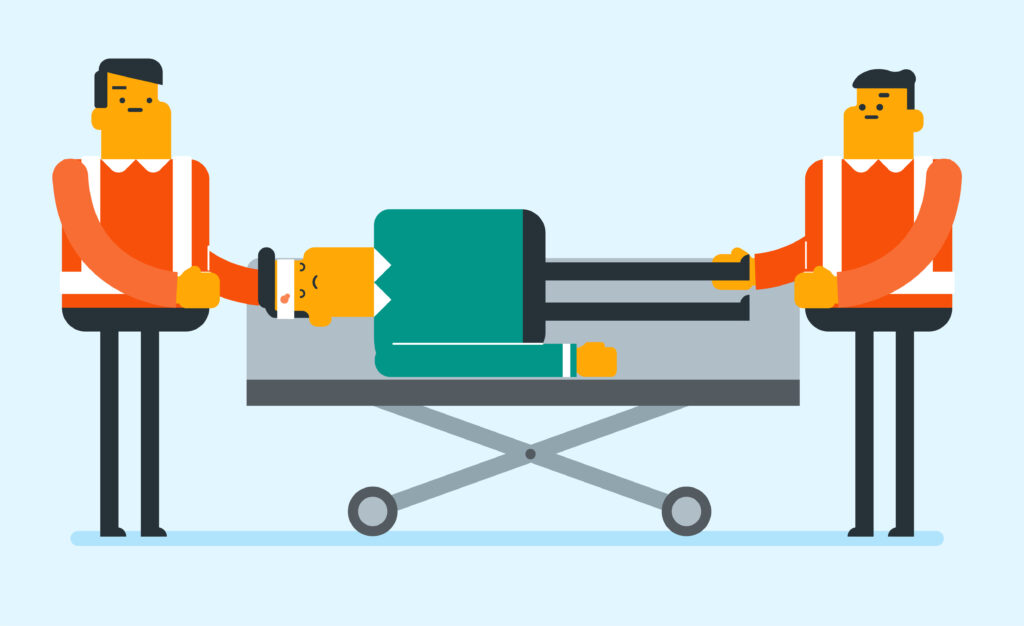
YMYL(Your Money or Your Life)とは、お金・医療・法律・健康・生活に影響する情報のこと。
- 金融・投資
- 医療・美容
- 法律相談
- 育児・介護
- 安全対策
これらのジャンルは、E-E-A-Tが低いと上位表示が極端に難しいです。
逆に、雑記ブログやエンタメ系コンテンツでは、E-E-A-Tの重要度は比較的低めです。
ただし、Googleは常に信頼できる情報を優遇する方針なので、どんなジャンルでも意識しておくべきです。
まとめ|E-E-A-TはこれからのSEOの土台
- E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の4要素
- 検索品質評価ガイドラインに基づき、Googleはこれらを評価して順位を決定
- 特にYMYLジャンルではE-E-A-Tが必須レベル
- 被リンクやキーワードだけでは評価されない時代になった
これからのSEOでは、「誰が、どんな経験や専門性をもって、どんな風に伝えるか」がますます重視されます。
自分や自社のサイトを見直して、E-E-A-Tの観点から改善できる部分がないか、ぜひチェックしてみてください。


